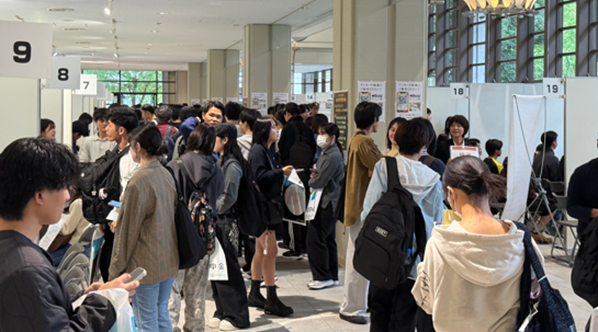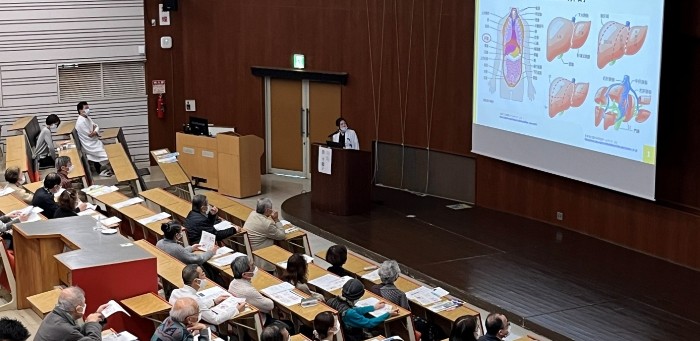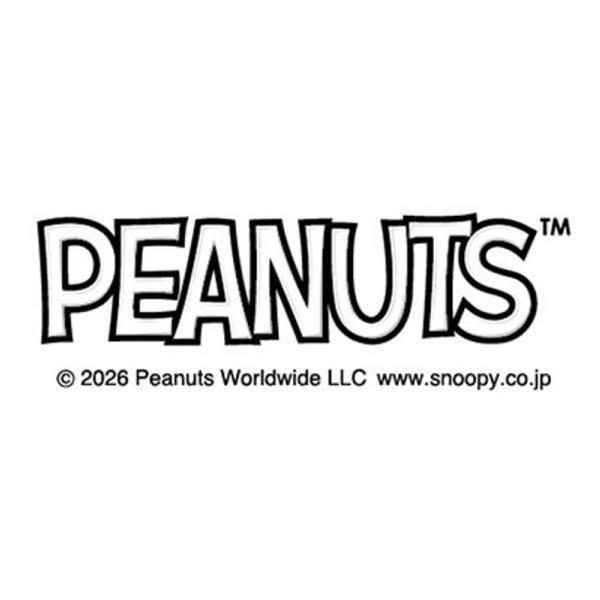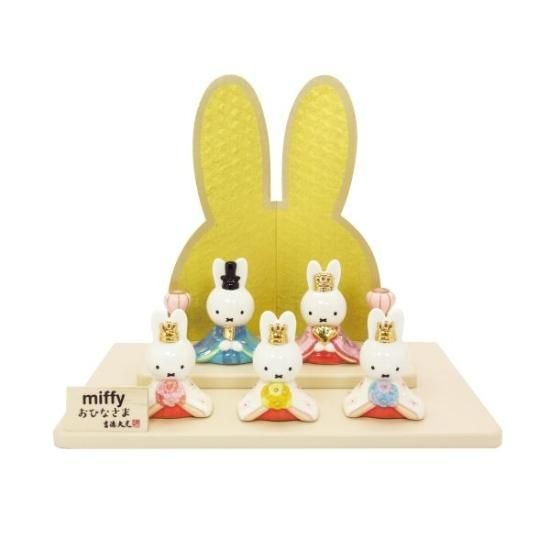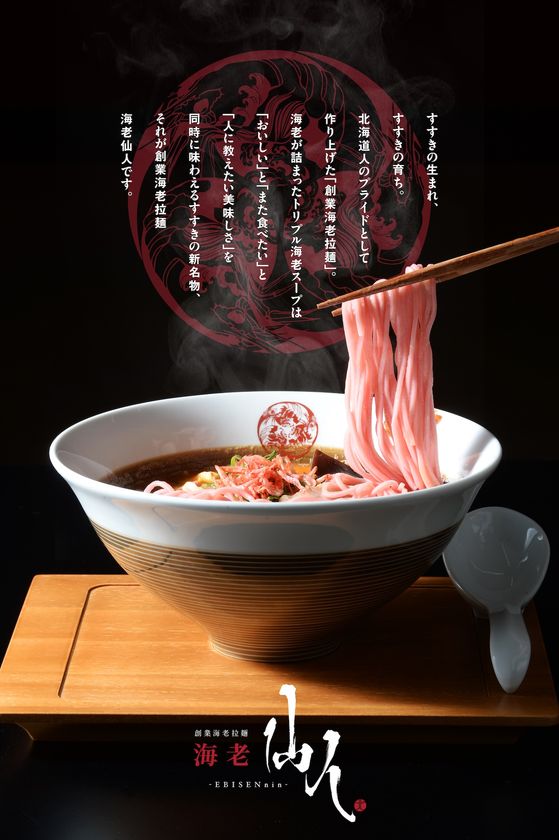光の利用効率が約500%となる革新的な光触媒反応で過酸化水素を合成 太陽光エネルギーを用いた物質合成への応用に期待

近畿大学理工学部応用化学科准教授 副島哲朗、大学院総合理工学研究科博士後期課程2年 エン ヨウソウ、理工学部応用化学科講師 杉目恒志、学校法人近畿大学法人本部管理部(いずれも大阪府東大阪市)技術課長 納谷真一、名古屋大学未来社会創造機構(愛知県名古屋市)客員教授 多田弘明らの研究グループは、次世代のクリーン燃料として注目される過酸化水素を、再生可能なエネルギーを用いて合成する研究に取り組んでいます。
このたび、簡便な方法で合成したナノ複合光触媒※1 によって、世界最高濃度の3倍以上となる過酸化水素が生成され、その現象は光の利用効率が約500%となる革新的な光触媒反応であることを明らかにしました。本研究成果により、太陽光という希薄なエネルギー源を用いた実用レベルの物質合成を達成するための、新たな触媒開発に貢献することが期待されます。
本件に関する論文が、令和7年(2025年)5月2日(金)に、イギリスの学術機関である王立化学会(Royal Society of Chemistry)が出版する化学分野の国際学術誌"Chemical Science(ケミカル サイエンス)"に掲載されました。
【本件のポイント】
●市販の酸化亜鉛のナノ粒子とアンチモンドープ酸化スズのナノ粒子※2 を水に加えて乾燥・焼成するという簡便な方法で、ナノ複合光触媒が形成されることを発見
●得られたナノ複合光触媒をもとに世界最高濃度の3倍以上となる過酸化水素が生成され、その現象は光の利用効率が約500%となる革新的な光触媒反応であることを解明
●太陽光という希薄なエネルギー源を用いた、実用レベルの物質合成への応用が期待できる研究成果
【本件の背景】
ナノサイズ(ナノメートル=10億分の1メートル)の材料は、単独では役に立たなくても、異なるものと組み合わせたナノ複合材料とすることで、高い性能を発揮することがあります。近年、新しい機能を求めて、さまざまなナノ複合材料が合成されています。ナノ複合材料の応用例の一つに、照射される光を用いて有用な化学反応を起こす光触媒があります。これは、本多―藤嶋効果※3 の発見に端を発した水の完全分解光触媒など、我が国が最先端をリードしている分野の一つです。
一方、オキシドールとして知られている過酸化水素は、化成品の合成や半導体の洗浄、パルプの漂白など幅広い分野で利用されており、また、次世代燃料電池用のクリーン燃料としても注目されています。平成22年(2010年)に同研究グループが「光触媒によるクリーンな過酸化水素合成」を提案(J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 7850. DOI:https://doi.org/10.1021/ja102651g)して以来、光触媒の一大トレンドとして世界中で研究開発競争がなされています(図1)。
しかし、精密なナノ複合材料の合成には高価な機器が必要で、手順が複雑であり、太陽光のエネルギーも希薄であることなどから、実用化には至っていません。そこで、簡便な方法で作製でき、高い光利用効率を持つ光触媒の開発が求められています。

【本件の内容】
研究グループは、市販されている酸化亜鉛のナノ粒子とアンチモンドープ酸化スズのナノ粒子を水に加えて乾燥・焼成するだけで、ナノ複合光触媒が形成されることを見出しました。得られたナノ複合光触媒をエチルアルコールを含む水に加え、酸素ガスを吹き込みながら光を照射したところ、非常に速い速度で過酸化水素が生成し、これまでの世界最高濃度の3倍以上を達成しました。反応への光の利用効率は約500%であり、これまでの光触媒の常識では説明できない現象であることが明らかとなりました。
さらに、光電気化学測定※4 やラジカル補足剤※5 を用いた実験、同位体※6 を用いた反応により、本現象が光触媒とラジカル連鎖反応の組み合わせによる革新的な光触媒反応であることを明らかにしました。
今後、太陽光という希薄なエネルギー源で駆動する実用レベルの物質合成に向けての応用が期待されます。
【論文掲載】
掲載誌 :Chemical Science(インパクトファクター:7.6@2024)
論文名 :Photocatalytic Hydrogen Peroxide Production
with an External Quantum Yield of Almost 500%
(外部量子収率500%の光触媒的過酸化水素合成)
著者 :Yan Yaozong1、納谷真一2*、杉目恒志1,3、多田弘明4*、副島哲朗1,3*
*責任著者
所属 :1 近畿大学大学院総合理工学研究科、2 学校法人近畿大学法人本部管理部、
3 近畿大学理工学部応用化学科、4 名古屋大学未来社会創造機構
論文掲載:https://doi.org/10.1039/D5SC01447F
DOI :10.1039/D5SC01447F
【本件の詳細】
過酸化水素は、化成品の合成や半導体の洗浄、パルプの漂白など幅広い分野で利用されており、次世代燃料電池用のクリーン燃料としても注目されています。現在の工業的合成法であるアントラキノン法は、水素ガスを原料として大規模プラントや有機溶剤を必要とするため、よりクリーンで安価な合成法の開発が望まれています。その一つの大きな候補が、太陽光を利用した光触媒による合成プロセスであり、世界各国で活発に研究開発が進められています。しかし、精密なナノ複合材料の合成には高価な機器が必要で手順も複雑であること、また、太陽光のエネルギーが希薄であることなどから、実用化には至っていません。
研究グループは、グリーン過酸化水素合成※7 について研究する中で、市販されている酸化亜鉛(ZnO)のナノ粒子と、アンチモンドープ酸化スズ(ATO)のナノ粒子を水に加えて乾燥・焼成するだけで、ナノ複合光触媒「ATO/ZnO」が形成されることを見出しました。さらに、その現象は、ZnOがマイナス、ATOがプラスに帯電するために起こることを明らかにしました(図2)。

得られたATO/ZnOを、エチルアルコールを含む水に加え、酸素ガスを吹き込みながら光照射を行ったところ、過酸化水素がきわめて高速に生成し、24時間で162mmol/Lという濃度の過酸化水素を生成しました(図3)。これは、これまでの世界最高濃度である51mmol/Lの3倍以上となります。さらに、光の反応への利用効率である外部量子収率は約500%であり、これまでの光触媒の常識では説明できない現象であることが明らかとなりました。
ZnOのナノロッドアレイ※8(図4)を光電極に用いた光電気化学測定では、通常の酸素の還元による過酸化水素生成に加え、酸化側でもファラデー効率※9 が200%を超える量で過酸化水素が生成していることがわかりました。さらに、ラジカル補足剤を用いた実験や同位体を用いた反応により、エチルアルコールを酸化して生成したラジカルが連鎖反応を起こし、次々と過酸化水素を生成する、新たな光触媒反応系であることが明らかとなりました(図5)。光触媒とラジカル連鎖反応の組み合わせにより、従来の発想では得られない高い活性が達成されたといえます。これにより、実用レベルの物質合成に対する足かせとなっていた、希薄な太陽光エネルギーによる制限を打開することが可能となり、今後の触媒開発に様々な示唆をもたらすことが期待できます。

【研究者のコメント】
副島哲朗(そえじまてつろう)
所属 :近畿大学理工学部応用化学科
近畿大学大学院総合理工学研究科
職位 :准教授
学位 :博士(工学)
コメント:本研究は、無機化学と有機化学の融合であり、これを物理化学的手法により解明した、まさに多様性の力によって得られた成果です。近年注目を集めるグリーン過酸化水素合成の分野に革新をもたらすものであるのと同時に、光の利用効率に上限がないことは、太陽光という希薄なエネルギー源で駆動する実用レベルの物質合成プロセス実現に向けた大きな一歩になると期待できます。
【研究支援】
本研究は、日本学術振興会による科研費(課題番号21K05236、23K04545)ならびに双葉電子記念財団、加藤科学振興会、日本板硝子材料工学助成会、泉科学技術振興財団による研究助成の支援を受けて行われました。
【用語解説】
※1 光触媒:触媒とは、特定の化学反応を速める性質がある物質で、その物質自体は化学反応の前後で変化しないもの。化学工業的にきわめて重要な物質で、代表的なものとして、化学製造における基礎的な窒素源になるアンモニアは、鉄系の化合物が触媒となり製造が可能となる。光触媒は、光照射により触媒作用を発現する。
※2 酸化亜鉛のナノ粒子とアンチモンドープ酸化スズのナノ粒子:酸化亜鉛は化粧品や抗菌・抗ウィルス材料として、アンチモンドープ酸化スズは近赤外線を吸収する無機材料として遮熱ガラスコーティングなどの目的で市販されている。
※3 本多―藤嶋効果:酸化チタン電極に光を当てると、水が酸素と水素に分解するという効果。酸化チタン単独では不可能で、ナノ複合体にするか電圧をかけながら光照射を行う必要がある。
※4 光電気化学測定:光を当てた時に起こる化学反応を電気信号として測定する方法。本件では、酸化亜鉛電極に光を当てた際にエチルアルコールが酸化されること、そして、酸素が還元されて過酸化水素が発生することを電流として検出している。その電流から考えられる量の2倍以上(200%以上)も過酸化水素が生成していることが、連鎖反応が進行していることの証拠となる。
※5 ラジカル補足剤:添加することで、反応中に生じるラジカルと結合し、連鎖反応を止めることができる試薬。本件では、このラジカル補足剤を加えると、過酸化水素の生成量が劇的に低下することから、ラジカル連鎖反応が進行していることを示している。
※6 同位体:原子番号が等しく質量数が異なる元素(原子核の陽子数が同じで、中性子数が異なる元素)を同位体という。化学的性質はほぼ同じであるが、その少しだけ違う性質を利用することで反応のメカニズムを明らかにすることができる。
※7 グリーン過酸化水素合成:環境に悪影響を与えることなく、再生可能な資源およびエネルギーを用いて過酸化水素を合成すること。
※8 ナノロッドアレイ:ナノサイズ(ナノメートル=10億分の1メートル、ナノサイズとは数~数100ナノメートルの大きさのこと)の直径を有する棒状物質のことをナノロッドといい、このナノロッドが基板から高密度に成長あるいは周期的に配向成長したものをナノロッドアレイと呼ぶ。
※9 ファラデー効率:電気化学反応において、流れた電流量に対する生成物の割合。通常、理想的に全ての電子が反応に使用されたとすると100%となる。
【関連リンク】
理工学部 応用化学科 准教授 副島哲朗(ソエジマテツロウ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/378-soejima-tetsurou.html
理工学部 応用化学科 講師 杉目恒志(スギメヒサシ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/2530-sugime-hisashi.html