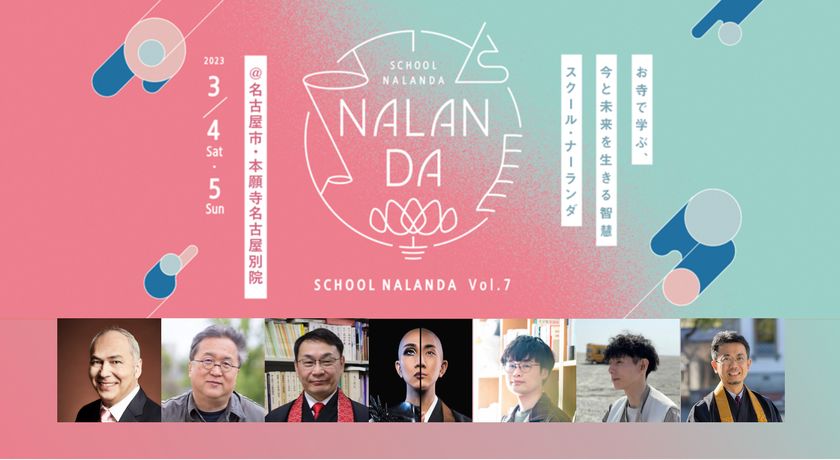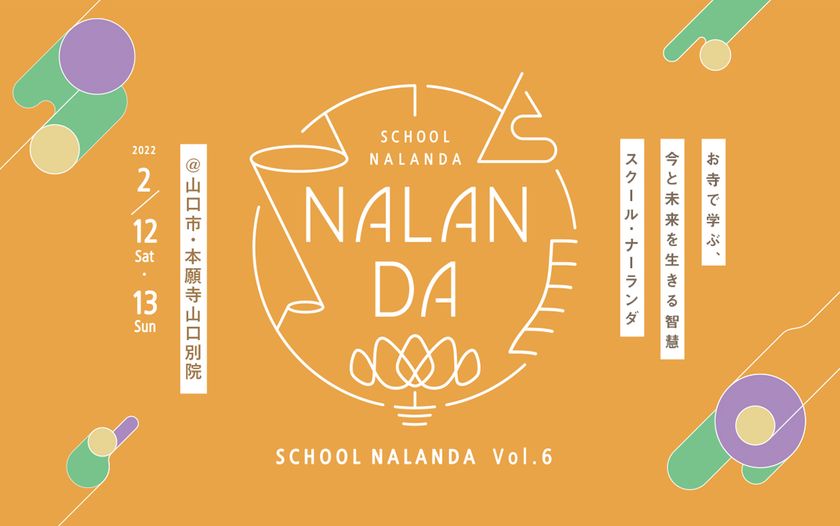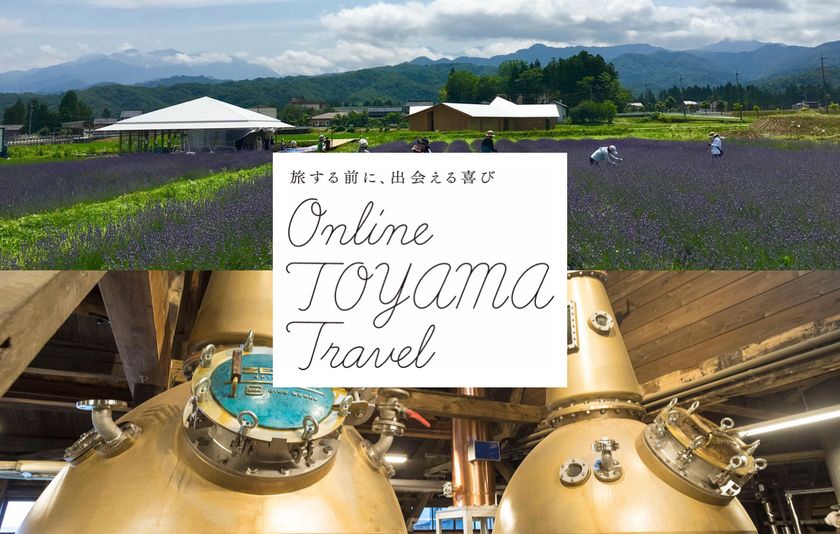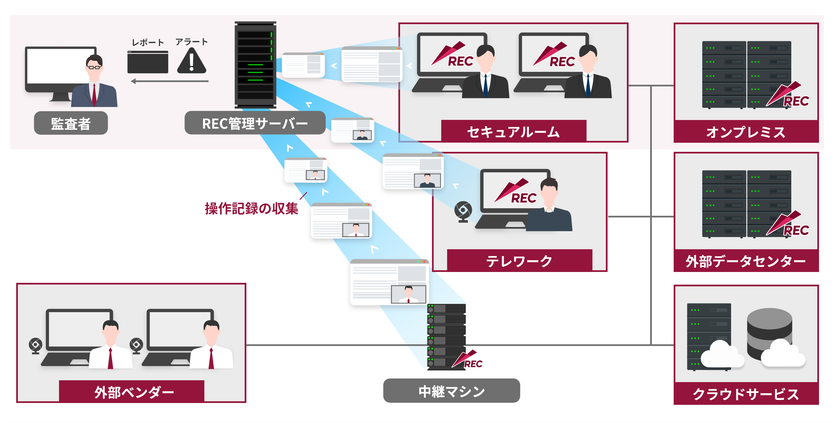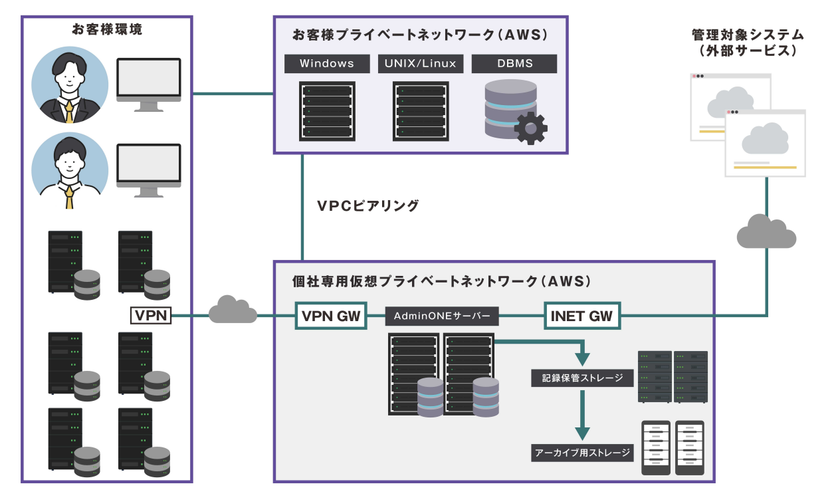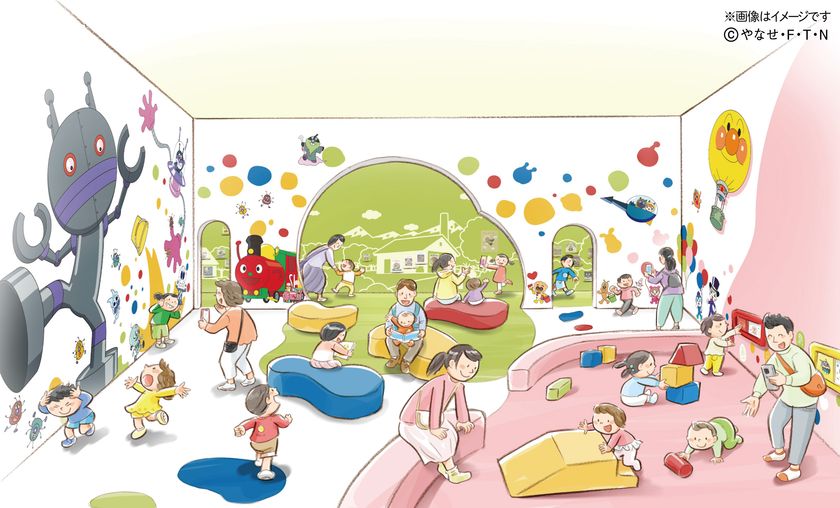法隆寺の門外不出の像を再現! 展覧会を、今春に高岡市で開催(3/10~20)
伝統技術と最新科学技術で忠実に再現! 門外不出の釈迦三尊像を再現した像を間近に拝める、貴重な11日間
イベント
2017年3月6日 18:00富山県高岡市、南砺市および東京藝術大学は平成27年度から、産学官連携で国宝 法隆寺釈迦三尊像(以下、「釈迦三尊像」)の再現に取り組んできました。東京藝術大学が法隆寺および文化庁より特別に許可を得て計測した釈迦三尊像の3Dデータをもとに、3Dプリンターで原型を制作し、高岡銅器(高岡市)の伝統技術による鋳造と、井波彫刻(南砺市)の伝統技術による台座の制作を経て、現在東京藝術大学にて完成に向けた仕上げを行っています。
学術的な最新研究成果と、長い年月で培われた職人の経験と感性が相互に補い合い、本物に限りなく同質なもので複製することで、日本の芸術文化と地域の伝統技術の継承や、歴史的美術工芸品の未来の復元技術の発信につなげていきます。
この完成した再現物を、富山県高岡市で開く展覧会「法隆寺 再現 釈迦三尊像展 - 飛鳥が告げる未来 -」〔3月10日(金)~20日(月・祝)〕で初公開します。普段法隆寺では像の裏側は見られず、正面からも金網越しでしか見ることができません。この展示では、東京藝術大学が別途再現した法隆寺金堂の壁画と、今回再現した仏像を実際の法隆寺金堂に近い配置で設置し、間近に拝むことができます。また、3Dプリンターで制作された原型や、鋳造工程の石膏型も展示します。
URL: http://www.city.takaoka.toyama.jp/sanki/sangyo/shinsangyo/shakasanzon.html
■日本遺産のまち高岡
富山県高岡市は人口約175,000人の県西部の中心のまち。「加賀藩の台所」として、また、400年以上続く「鋳物のまち」として栄え、豊かな町民文化と、ものづくりの技がいまに受け継がれてきたまち。平成27年4月、文化庁が認定する「日本遺産」に、高岡市が提案するストーリー「加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡 ―人、技、心―」が、全国18件のうちのひとつとして認定されました。
■展覧会は雅楽演奏で幕を明け、会期中は職人による実演も!
<展覧会「法隆寺 再現 釈迦三尊像展 - 飛鳥が告げる未来 -」>
法隆寺の法要で雅楽が奏されることにちなみ、展覧会前日(3月9日)のオープニングでは、江戸時代から続く高岡の雅楽団体「洋遊会」と東京藝術大学の洋楽演奏者が、展覧会の開催を記念して今回新しく作曲された雅楽も演奏します。また、実際の制作に携わった高岡銅器や井波彫刻の職人たちによる実演・ギャラリートークも必見です。
◆展覧会名 :法隆寺 再現 釈迦三尊像展 - 飛鳥が告げる未来 -
◆日時 :平成29年3月10日(金)~20日(月・祝)
10:00~18:00(入場は17:30まで)
◆場所 :ウイング・ウイング高岡 4階ホール、ホワイエ
(富山県高岡市末広町1番7号)
◆特別協力 :聖徳宗総本山法隆寺、東京藝術大学社会連携センター、
東京藝術大学COI拠点
◆総合監修 :宮廻 正明
◆キュレーター:伊東 順二
◆空間構成 :横山 天心(富山大学芸術文化学部 准教授)
◆料金 :観覧無料
◆主催 :400年を超える高岡市の鋳物技術と600年を超える南砺市の
彫刻技術を活用した地場産業活性化モデルの
構築・展開事業推進協議会
◆一般の方のお問合せ:上記協議会事務局(高岡市産業企画課内)
TEL : 0766-20-1395
FAX : 0766-20-1287
Email: sangyo@city.takaoka.lg.jp
画像:
・高岡銅器の伝統技術による鋳造直後の中尊と大光背
https://www.atpress.ne.jp/releases/123586/img_123586_3.jpg
・東京藝術大学が計測した3Dデータから制作した中尊の樹脂製の原型
https://www.atpress.ne.jp/releases/123586/img_123586_2.jpg
・井波彫刻の伝統技術による制作直後の宣字座
https://www.atpress.ne.jp/releases/123586/img_123586_4.jpg
<会期前・会期中のイベント詳細>
【オープニング】
定員100名/申込先着順
◯日時:3月9日(木)17:30~19:45
◯場所:ウイング・ウイング高岡 4階ホール
・プログラム
17:30~18:15 ●内覧会
●洋遊会と東京藝術大学のコラボレーションによる雅楽演奏
(洋遊会:江戸時代からの歴史がある富山県高岡市の雅楽団体)
18:15~19:45 ●ご挨拶
高橋 正樹(高岡市長)/田中 幹夫(南砺市長)
●トークイベント(敬称略・五十音順)
伊東 順二(本企画キュレーター・
東京藝術大学社会連携センター 特任教授)
岩崎 孝進(井波彫刻協同組合 理事長)
梶原 壽治(伝統工芸高岡銅器振興協同組合理事長)
隈 研吾(建築家・東京大学教授)
高橋 正樹(高岡市長)
田中 幹夫(南砺市長)
宮廻 正明(東京藝術大学大学院教授・
学長特命・社会連携センター長)
【ギャラリートーク】
定員各50名/申込先着順
◯日程:3月11日(土)/3月18日(土)
◯場所:ウイング・ウイング高岡 4階ホール
・3月11日(土) 「彫刻技術による釈迦三尊像の再現」
◯時間:14:00~14:45
大石 雪野(彫刻家・東京藝術大学 特任研究員)
南部 克紀(井波彫刻協同組合 常務理事)
深井 隆(東京藝術大学美術学部彫刻科 教授)
・3月18日(土) 「金工技術による釈迦三尊像の再現」
◯時間:14:00~14:45
相原 健作(金工作家・東京藝術大学特任研究員)
嶋 安夫(伝統工芸高岡銅器振興協同組合 直前理事長)
丸山 智巳(東京藝術大学美術学部工芸科鍛金研究室 准教授)
【職人による実演】
◯日程:3月11日(土)/3月18日(土)
◯場所:ウイング・ウイング高岡 4階ホワイエ
・3月11日(土) 「彫刻師による実演」
◯時間:13:30~15:30
台座を制作した彫刻師が実際に彫刻する様子をご覧いただけます。
実演者:井波彫刻協同組合 彫刻師
・3月18日(土) 「彫金師による実演」
◯時間:13:30~15:30
大光背の光背銘を彫金した職人が実際に彫金する様子をご覧いただけます。
実演者:伝統工芸高岡銅器振興協同組合 彫金師
■古代の人が込めた思いを、現代に。釈迦三尊像再現物ができるまで
釈迦三尊像は、本尊・左右脇侍の三尊からなる止利様式の仏像で、飛鳥彫刻の代表作。聖徳太子の病気平癒祈願のため、日本最初の仏師と言われる鞍作止利が制作を委嘱され、太子の没後625年に完成したもの。釈迦三尊像の大胆で簡潔な造形が醸しだす美と慈愛に満ちた姿は、鋳造の銅の厚みの均一性や鉄心の抜き取りなど、当時最先端の技術に支えられています。東京藝術大学の最新技術と、伝統工芸高岡銅器振興協同組合、井波彫刻協同組合の職人たちの伝統技術の掛け合わせによる、約2年におよぶ再現の軌跡を紹介します。
・STEP1 国宝を計測・解析し、原型を作成(東京藝術大学)
国宝 法隆寺釈迦三尊像を3D計測し、学術的知見からデータを補完。より精度の高い3Dデータを作成し、原型を制作しました。
・STEP2 銅像部分の鋳造(高岡銅器/富山県高岡市)
<伝統工芸高岡銅器振興協同組合>東京藝術大学提供の原型を基に、中尊、脇侍、光背を鋳造しました。
・STEP3 台座の木工・木彫(井波彫刻/富山県南砺市井波)
<井波彫刻協同組合>本尊を支える宣字座(木製の台座)を制作しました。
・STEP4 仕上げ(東京藝術大学)
鋳造した銅像の造形を仕上げ、1300年の経年変化による傷や摩耗、古色を施しました。
■文化財の修復・復元で活躍する、最新技術と伝統技術。
・東京藝術大学
創立以来130年間、優れた芸術家や教育者、研究者を輩出するとともに、文化財の保護と継承にも努めてきました。2010年には、模写や模刻の伝統技術に現代のデジタル技術を融合させ、高精度かつ同素材同質感で文化財を複製・再現する技術を開発。同学COI拠点では、芸術と科学技術を統合した高精度な文化財の複製を制作し、流出または消失した世界中の文化財の復元を目指しています。
・高岡市(高岡銅器)
高岡の鋳物技術の歴史は、約400年前、高岡を開町した加賀前田家二代当主・前田利長公が、現在の金屋町に7人の鋳物師を呼び寄せ、厚い保護や特権を与えたことに始まります。当初は鉄が中心でしたが、江戸中期より銅が用いられ、美術品や仏具、茶釜などの生産が盛んになりました。これらの商品を売る商人や問屋も次第に力をつけ、商人町を形成。今も残る山町筋の土蔵造りの町並みに、その名残を見ることができます。高岡の鋳物技術は、世界遺産に登録されているスペイン・バルセロナにあるグエル邸の「龍の門」の鐘の復元に用いられるなど、歴史的記念碑や工芸品の修復・再現に期待されています。
・南砺市(井波彫刻)
瑞泉寺の門前町として栄えた井波。大火で焼失した瑞泉寺再建のために京都より彫刻師が招かれ、その技術を継いだ宮大工が今日の井波彫刻の礎を築きました。歴史的な木彫品の修復・復元等にもその技術が用いられ、現在名古屋城本丸御殿再建事業では、欄間に井波彫刻の技が光ります。
■TOPICS
<Event>
これであなたも曳山マニア 県内の曳山をスタンプラリーで巡ろう!
日本遺産に認定された高岡市のストーリーの構成文化財であり、昨年ユネスコ無形文化遺産にも登録された高岡御車山祭。今年の開催日は市内全小・中・特別支援学校が休みになるなど、町民たちの熱い思いが伺えます。そんな高岡御車山祭をはじめとした富山県内の曳山文化を、祭り当日以外も楽しんでもらおうと、曳山会館を巡る曳山マニアックガイドが作成されました。高岡御車山会館など、県内5カ所でゲットでき、曳山スタンプラリーも楽しめます。御車山と各地の曳山を比べ、祭りの魅力を感じてみませんか。
・高岡御車山祭
とき:5月1日
・曳山マニアックガイド・スタンプラリー
期間:3月1日~ 5月31日
費用:無料
※スタンプを集めると抽選でオリジナルグッズも当たる!
ガイド&スタンプラリー設置場所
(1)高岡御車山祭の御車山(高岡御車山会館)
(2)新湊曳山(川の駅新湊)
(3)城端神明宮祭の曳山(城端曳山会館)
(4)八尾曳山祭の曳山(富山市八尾曳山展示館)
(5)魚津のたてもん(ありそドーム)