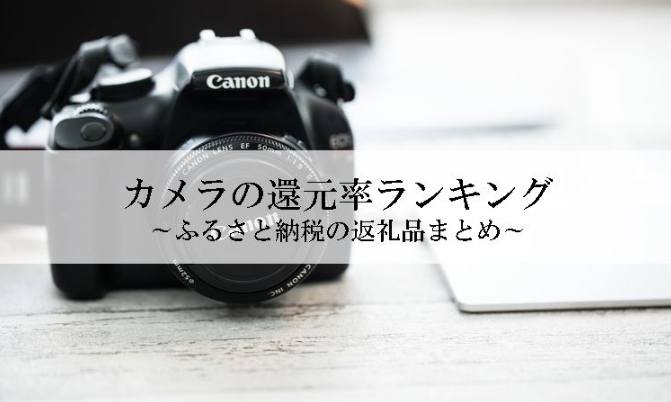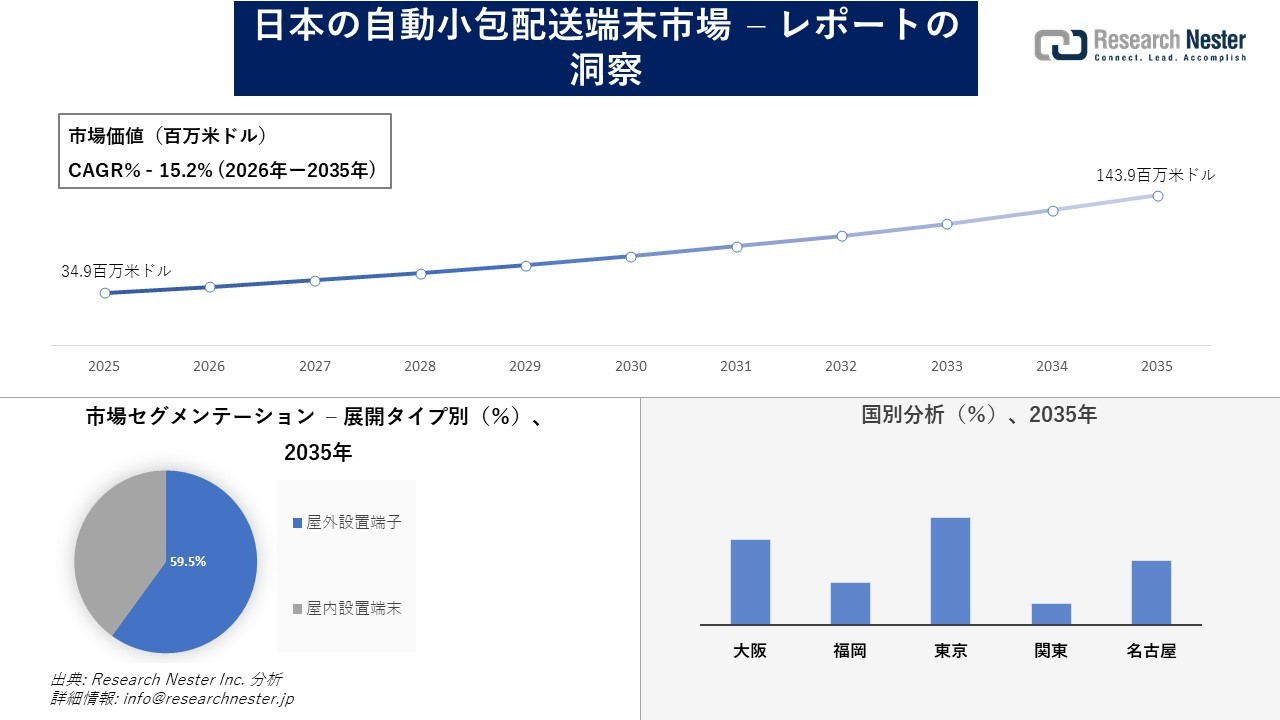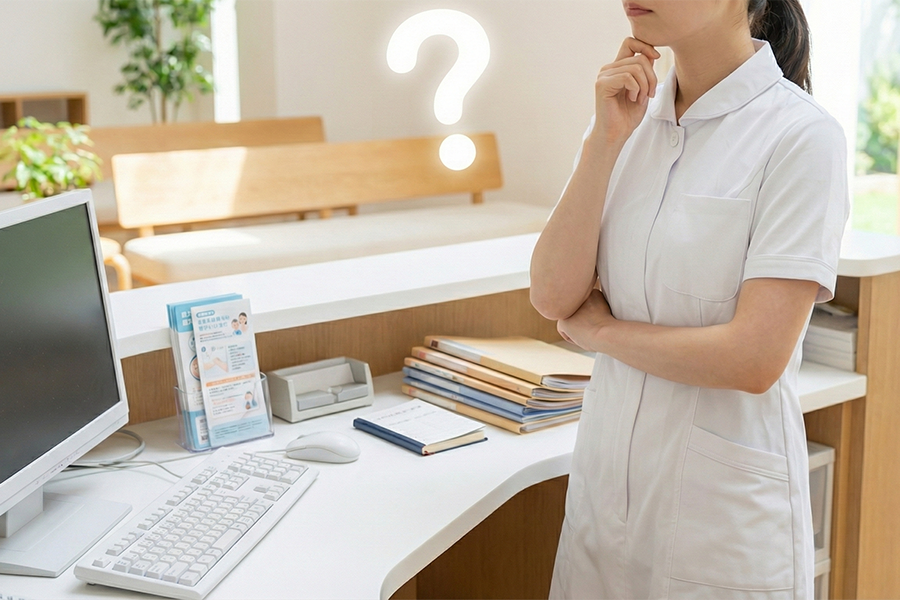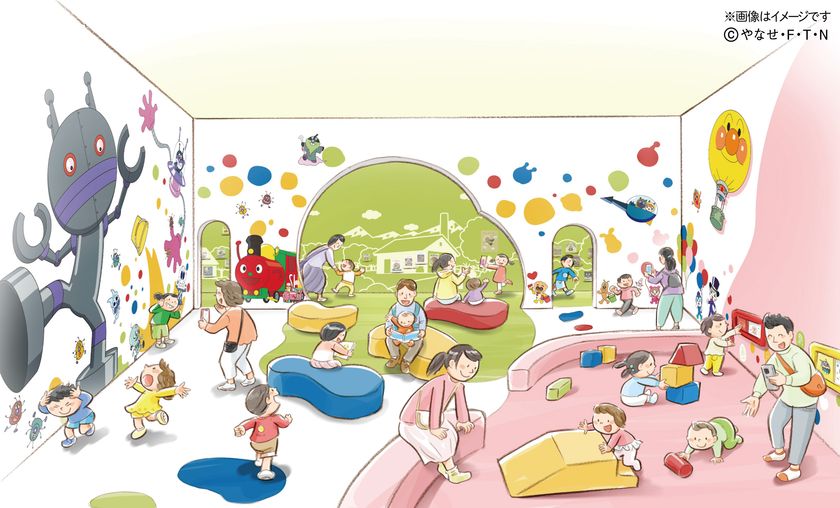《YouTube番組》量子力学から生命現象まで、 最先端で活躍する科学者たちが“学びの真髄”を語る! 撮り下ろしロング・インタビューの最新話が配信スタート
人類の“知”を更新する者たち―― 科学者たちはいったいなぜ、次々と新しいアイデアや発見を導くことができるのか? 普段は表立って語られない独自の思考法や姿勢から、 大小さまざまな“知の法則”を探る第4弾
2025年10月10日(金)20時より、YouTube番組『科学者たちはどう学ぶか』は第4回目となる動画を公開しました。公式YouTubeチャンネルのほか、各種Podcastでも配信予定です。
〈YouTube〉 https://youtu.be/K4xo-yffOCQ
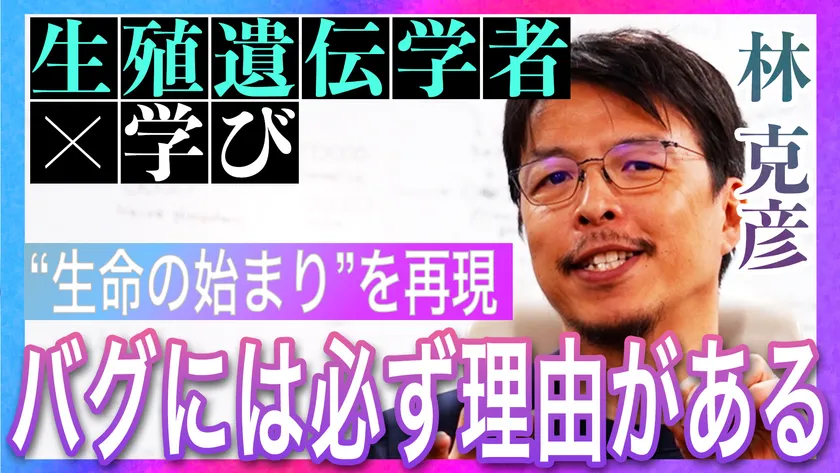
【生殖遺伝学者 林克彦 ~前編~】「生殖細胞は“死なない細胞”」「“条件がそろっていない”から発見がある」最先端の生殖遺伝学研究に挑む科学者の学びの核心に迫る
■新YouTube番組『科学者たちはどう学ぶか』
この番組は、第一線で活躍する科学者を訪ねて、学ぶ醍醐味やコツ、奥深さに迫るインタビュー番組です。科学の魅力はもちろんのこと、今を生きる人々に多様な学びのあり方を伝え、そして未来の学びをより良くするインタビュー・アーカイブを目指します。(制作:株式会社mK5)
〈YouTubeチャンネル〉 https://www.youtube.com/@kagakusya_manabu
【第1回:理論物理学界のトップランナーが語る 規格外の思考実験から生まれる学び】
第1回では、東京大学 物性研究所 教授で理論物理学者の押川正毅さんにご出演いただきました。最先端の物性理論を研究する世界的な理論物理学者に、自身の“学び”について詳しくインタビューした模様を配信中です。「現実の問題を解き明かすために、あえて“現実離れした思考実験”をする」、「現代物理学で欠かせない量子力学が“人類の学び”としてどう魅力的か」など、理論物理学者ならではの観点で貴重な話を伺っています。(2025年5月公開)
〈前編〉 https://youtu.be/tiM6ZHYTFGM
〈後編〉 https://youtu.be/vnK1sn0Y5qQ
【第2回:ハチ研究の第一人者が語る 観察対象と徹底的に向き合う学び】
第2回では、ハチ研究の第一人者で玉川大学 学術研究所 所長の小野正人さんに話を聞きました。スズメバチやミツバチなど多種多様なハチの生態について、行動学から生物資源としての応用面まで幅広く網羅する小野所長。昆虫が人類よりもはるかに長い“4億年の歴史”をもつ生物であることへの独自の眼差しや、実験やフィールドワークのなかで“先入観”や“色眼鏡”を捨てるために心がけている姿勢など、昆虫をより深く学び・研究するための様々な秘訣を伺っています。(2025年6月公開)
〈前編〉 https://youtu.be/qQWQfPmx07o
〈後編〉 https://youtu.be/Z1012vQWkPg
【第3回:ブラックホール観測研究の第一人者が語る 壮大なタイムスケールで進む学び】
第3回では、ブラックホール観測研究の第一人者である、国立天文台 水沢VLBI観測所 所長の本間希樹さんに話を聞きました。複数の電波望遠鏡のデータを合成するVLBI(Very Long Baseline Interferometry)という技術を使い、光すら吸い込むブラックホールを "撮影" する研究に取り組んできた天文学者は、どのように日々の学びと向き合ってきたのか?時間や空間の概念を超越するブラックホールの魅力や、壮大なタイムスケールで進行するプロジェクトに挑む姿勢について掘り下げます。(2025年7月公開)
■第4回【生殖遺伝学者 林克彦 ~前編~】「生殖細胞は“死なない細胞”」「“条件がそろっていない”から発見がある」最先端の生殖遺伝学研究に挑む科学者の学びの核心に迫る
第4回となる今回は、生殖遺伝学研究の最先端で活躍する、大阪大学大学院 医学系研究科 教授の林克彦さんに話を聞きました。精子や卵子といった“生殖細胞”の発生過程を培養条件下で再現し、遺伝情報を次世代に伝えるメカニズムの探求に取り組んできた林教授。2023年には、オスのマウスのiPS細胞から卵子を作ることに世界で初めて成功し、大きな注目を集めました。そんな第一線で活躍する生殖遺伝学者ならではの“学び”への向き合い方を尋ねると、他の様々な細胞とは異なる“生殖細胞”独自の特徴に対する興味や、“バグ”を積極的に取り入れる研究のアプローチが浮かび上がってきました。
(今回のキーポイント)
・生殖細胞は“死なない細胞”
・生殖細胞なのに“体の外”で研究する
・学びのルーツ 動物がいつもそばにいた
・研究の原点 大学時代の体外受精の実験
・“生命の始まり”に介入するということ など
〈前編〉 https://youtu.be/K4xo-yffOCQ
■出演者プロフィール
林克彦
大阪大学 大学院 医学系研究科 教授。文部科学大臣表彰 科学技術賞を受賞するなど最先端の生殖学研究を展開。精子や卵子といった"生殖細胞"の発生過程を培養条件下で再現し、遺伝情報を次世代に伝えるメカニズムの探求に取り組む。2023年には、オスのマウスのiPS細胞から卵子を作ることに世界で初めて成功。このオス由来の卵子を別のオスの精子と受精させることで"両親がオス"のマウスを誕生させる。絶滅危惧種の保全に役立つ可能性がある研究と高く評価され、同年、イギリスの科学誌『ネイチャー』の「今年の10人」に選出された。

インタビューの様子
■次回予告
第4回の後編は11月に配信予定です。