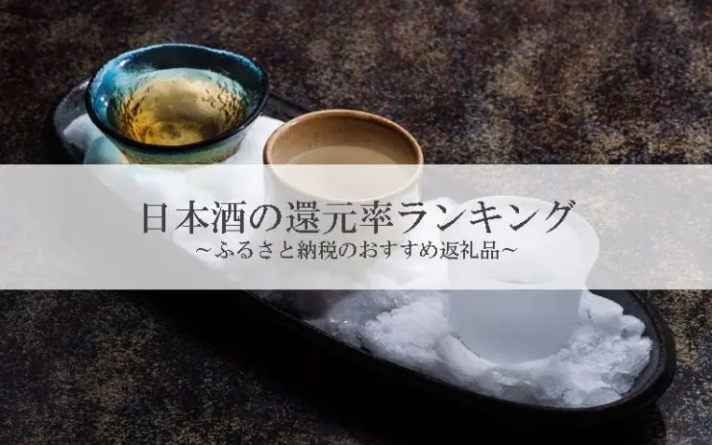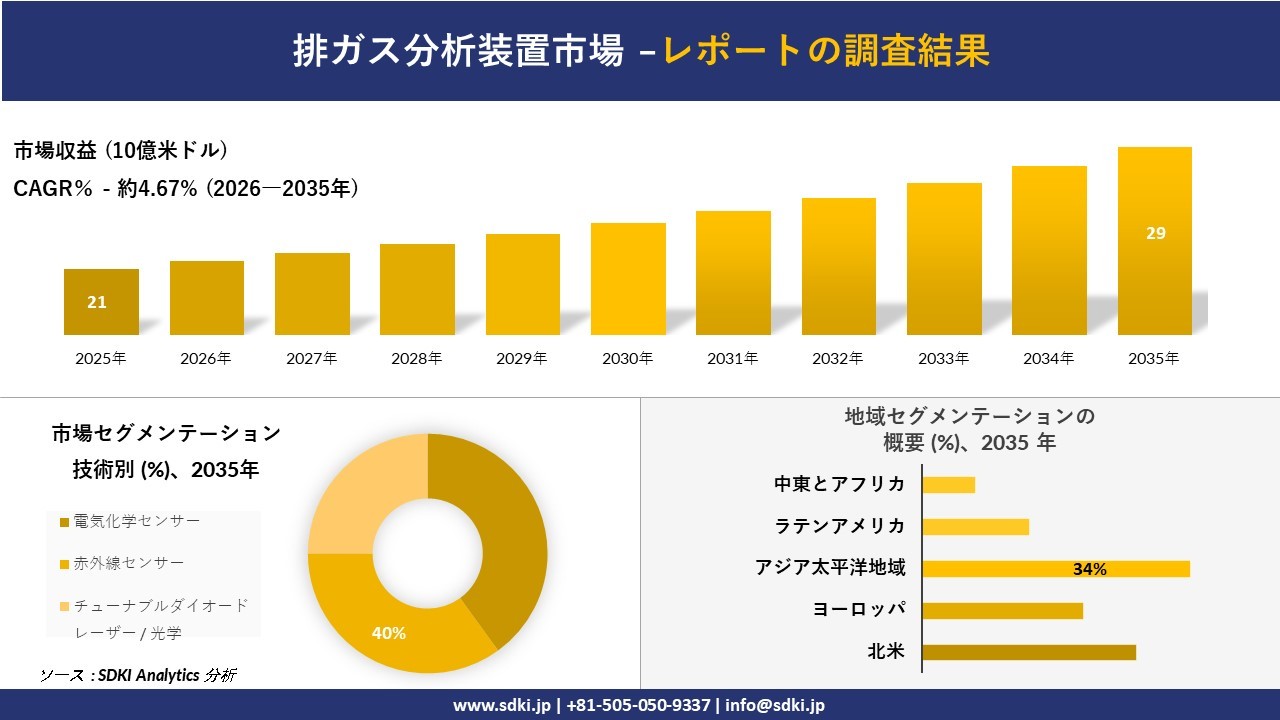アクアグリセロポリンが尿素・ホウ酸の透過性を制限する仕組みを解明 -遺伝子配列から活性予測を可能に-

【ポイント】
●細胞表面の膜タンパク質で水とグリセロールのチャネルであるアクアグリセロポリンAqp10が、選択的に尿素・ホウ酸を透過する仕組みを解明しました。
●比較進化生理学的な手法と分子計算による細孔構造予測により、尿素・ホウ酸を透過しないタイプのAqp10の構造上の特徴を明らかにしました。
●生物のゲノムから見つかる機能未知のアクアグリセロポリンの活性予測に貢献することが期待されます。
【概要】
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の永嶌鮎美助教、潮和敬大学院生(研究当時)、加藤明准教授らの研究チームは、同 古田忠臣助教、近畿大学 農学部の西原秀典准教授と共同で、水とグリセロールのチャネルとして知られるアクアグリセロポリン(用語1)Aqp10がグリセロール以外の小分子(尿素・ホウ酸)の透過を制御する仕組みを明らかにしました。これまで、アクアグリセロポリンが水以外の小分子の透過を制御するメカニズムはよく分かっていませんでした。今回、尿素・ホウ酸を輸送するタイプと輸送しないタイプの2種類のAqp10を持つ魚類に着目し、その構造上の違いを比較進化生理学(用語2)的な手法と分子計算による細孔構造予測(用語3)により解析しました。その結果、チャネルの細孔を形成するアミノ酸残基のかさ高さと尿素・ホウ酸透過性とに逆相関の関係が存在することを発見し、変異体の解析によりその法則を明らかにしました。
本研究はアクアグリセロポリンの水以外の小分子の透過の選択性を担う分子機構の理解を深めます。また、本研究で用いた手法は、公共ゲノムデータベースに記述されたさまざまな機能未知のアクアグリセロポリンの活性予測に役立てることができます。
本研究の成果は、2025年8月25日に米国生理学会が発行する「American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology」に掲載されました。
【背景】
アクアポリン(Aqps、用語4)は生物に広く分布する水チャネルのファミリーであり、水特異的な透過性を持つAqp(狭義Aqp、classical Aqp)、水に加えてグリセロールなど小さな無電荷溶質を透過するアクアグリセロポリンなどに分類されます[参考文献1]。代表的なアクアグリセロポリンには、ヒトのAqp-3、-7、-9、-10などが含まれます(以下、ここではタンパク質略称は最初の文字を大文字で、遺伝子略称は小文字とイタリック体で表記します)。アクアグリセロポリンのうち、Aqp-7、-9、および-10はグリセロールに加えて尿素やホウ酸も透過します。脊椎動物の過半数を占める条鰭類(用語5)に属する魚類は、ごく一部の例外を除き、二つ以上のAqp10遺伝子(aqp10)のパラログ(用語6)を持ちます。これらのパラログは条鰭類の祖先におけるタンデム重複により生じたaqp10.1とaqp10.2に由来しています[参考文献2]。Aqp10.1は四肢動物(用語7)のAqp10と同様に水、グリセロール、尿素、ホウ酸を透過しますが、Aqp10.2は水とグリセロールを透過する一方、尿素・ホウ酸を透過しない、もしくは弱く透過する性質を持ちます[参考文献3]。また魚類のAqp8は水、尿素、ホウ酸などを透過しますが、グリセロールは透過しません。これらの結果は、Aqpによるグリセロールと尿素・ホウ酸の透過性は異なるメカニズムで制御され、また、尿素とホウ酸の透過性は同じメカニズムで制御されていることを示唆しています。そこで本研究では、Aqp10.1とAqp10.2の溶質透過性の違いを生み出すメカニズムの解明を試みました(図1)。
【研究成果】
Aqp10.1とAqp10.2のアミノ酸配列が持つ特徴を明らかにするため、さまざまな条鰭類のゲノムデータベースからAqp10.1とAqp10.2の配列を集めて分子系統解析を行い、それぞれの祖先配列(用語8)を推定しました。同時に四肢動物Aqp10の祖先配列も推定しました。次に、推定した祖先配列の立体構造とその細孔構造を分子計算により予測したところ、二つの重要な発見をしました。一つ目として、Aqpに存在する水や溶質を透過する際の通り道となる細孔は、四肢動物Aqp10と条鰭類Aqp10.1では大きく、条鰭類Aqp10.2では小さいことを見出しました。二つ目として、細孔に存在することが知られる芳香族/アルギニン(ar/R)選択フィルターにおいて、それらの形成に関与する4つのアミノ酸残基の分子量の総和が四肢動物Aqp10と条鰭類Aqp10.1では小さく、条鰭類Aqp10.2では大きいことを見出しました(図2)。これらの発見から、条鰭類Aqp10.2はar/R選択フィルターに大きなアミノ酸残基を用いることで細孔を狭め、尿素・ホウ酸の透過性を減弱させたり無くしたりしている可能性が示唆されました。

続いて、この可能性を実証するために、ゼブラフィッシュAqp10.2の変異体を作製し、その活性を解析しました。ゼブラフィッシュAqp10.2は、ar/R選択フィルターを形成するアミノ酸残基の1位と3位にフェニルアラニン残基(F)、チロシン残基(Y)といった大きなアミノ酸残基を持っています。そこでこれらを小さなアミノ酸残基であるグリシン残基(G)やアラニン残基(A)に置換した変異体をそれぞれ作製してアフリカツメガエル卵母細胞に発現させ、水、グリセロール、尿素、ホウ酸の透過性を測定しました。その結果、水とグリセロールの透過性は野生型と変異体のどちらも高いことが確認された一方、尿素・ホウ酸の透過性は野生型では低く、変異体では高いことが確認されました(図3)。これらの結果から、Aqp10.2のar/R選択フィルターを形成する1位と3位のアミノ酸残基の両方がかさ高いアミノ酸残基であることが、尿素・ホウ酸透過性を減弱させたり無くしたりするために必要であることが示されました。

【社会的インパクト】
グリセロールや尿素は、体内のエネルギー代謝や窒素代謝における重要な代謝産物です。グリセロールは中性脂肪(トリアシルグリセロール)の加水分解によって生じ、体内では燃料となるほか、糖新生でグルコースを作る際の材料の一つになります。尿素は体内の窒素代謝で生じたアンモニアの無毒化により生じます。グリセロールと尿素は共に水溶性で小さく、電荷を持たないという共通の性質を持ちます。本研究により、グリセロールと尿素が輸送される際、体内でこの二つを区別する仕組みの一端が明らかになりました。また、ホウ酸はさまざまな生物にとって有益な微量元素である一方、過剰に摂取すると毒性を示します。本研究は細胞がホウ酸を吸収・排出したり、ホウ酸の侵入を防いだりするメカニズムの解明にもつながる可能性があります。今後、エネルギー代謝や窒素代謝、ホウ酸代謝の理解を進めることに対する貢献が期待されます。
【今後の展開】
本研究により、Aqp10の尿素・ホウ酸透過性がar/R選択フィルターを構成するアミノ酸残基の分子量の和から推定できることが明らかになりました。現在、数多くの脊椎動物種のゲノム配列が次々に解読されています[参考文献4]。これらゲノムプロジェクトの成果により、脊椎動物が持つ遺伝子構成の共通性や多様性が明らかになり、系統や種に特有の遺伝子重複や欠失が数多く存在することも明らかになりました。実際、aqpファミリーにおいても種や系統に特異的な数多くの遺伝子重複や欠失が存在します。また、重複した遺伝子がコードするタンパク質の一次構造(アミノ酸配列)も公共データベースとして公開されています。遺伝子重複により生じたパラログは、機能分化や機能獲得によりそれらがコードするタンパク質の活性が変化することがあるため、その活性を明らかにするためには生化学的手法による実験が必要です。本研究の成果により、ゲノムデータベースから得られる一次構造の情報からアクアグリセロポリンの活性を予測できることが明らかになり、ゲノムデータベースから得られる情報を精度よく解釈することに役立てることができます。
【付記】
本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究B(17H03870、21H02281、19H03272)および若手研究(21K14781)、ロッテ財団 奨励研究助成、東京科学大学挑戦的研究賞、東京科学大学生命理工学院竹田若手研究者賞、および東京科学大学ダイバーシティ推進室ワークライフ両立支援部門の「育児・介護中の研究者のためのアシスタント配置プログラム」の支援を受けて実施されました。
【参考文献】
[1] Borgnia M et al. Cellular and molecular biology of the aquaporin water channels. Annu Rev Biochem 68: 425-458, 1999. DOI: 10.1146/annurev.biochem.68.1.425
[2] Yilmaz O et al. Unravelling the Complex Duplication History of Deuterostome Glycerol Transporters. Cells 9: 2020. DOI: 10.3390/cells9071663
[3] Imaizumi G and Ushio K et al. Functional divergence in solute permeability between ray-finned fish-specific paralogs of aqp10. Genome Biol Evol 2023. DOI: 10.1093/gbe/evad221 東工大ニュース「Aqp10タンパク質の尿素・ホウ酸輸送活性の減弱が生じた進化上のタイミングを同定」
[4] Rhie A et al. Towards complete and error-free genome assemblies of all vertebrate species. Nature 592: 737-746, 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03451-0
【用語説明】
(1)アクアグリセロポリン:アクアポリンファミリーのうち、水のほかにグリセロールや尿素などの電荷を持たない低分子化合物を輸送する膜タンパク質。
(2)比較進化生理学:異なる生物の生理機能を比較し、生物の環境適応戦略や進化、それらの分子メカニズムを研究する学問分野。
(3)分子計算による細孔構造予測:過去に解かれたタンパク質の立体構造や予測構造を基に、細孔の構造や孔径を予測する手法。
(4)アクアポリン(Aqps):細胞膜に存在するタンパク質で、水分子を選択的に透過させる性質を持つ。1992年にピーター・アグレ(2003年ノーベル化学賞)らによって報告された。
(5)条鰭類:石灰質の骨を持つ脊椎動物のうち肉鰭類以外の群。魚類の大半を占める。
(6)パラログ:遺伝子重複によって生じた遺伝子群。
(7)四肢動物:脊椎動物のうち両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類を含む動物群。
(8)祖先配列:現存する生物の遺伝子配列と系統樹に基づいて計算によって推定された、共通祖先が過去に持っていたと考えられる遺伝子配列。
【論文情報】
掲載誌:American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
論文タイトル:Aquaporin 10 paralogs exhibit evolutionarily altered urea and boric acid permeabilities based on the amino acid residues at positions 1 and 3 in the ar/R region
著者:Ayumi Nagashima, Kazutaka Ushio, Hidenori Nishihara, Jin Akimoto, Akira Kato, and Tadaomi Furuta
DOI :10.1152/ajpregu.00212.2024
【研究者プロフィール】
永嶌鮎美(ナガシマアユミ)Ayumi NAGASHIMA
東京科学大学 生命理工学院 助教
研究分野:感覚生理学
西原秀典(ニシハラヒデノリ)Hidenori NISHIHARA
近畿大学 農学部 准教授
研究分野:ゲノム進化学
加藤明(カトウアキラ)Akira KATO
東京科学大学 生命理工学院 准教授
研究分野:比較進化生理学、分子生理学
古田忠臣(フルタタダオミ)Tadaomi FURUTA
東京科学大学 生命理工学院 助教
研究分野:生物物理学、分子モデリング
【関連リンク】
農学部 生物機能科学科 准教授 西原秀典(ニシハラヒデノリ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/2955-nishihara-hidenori.html