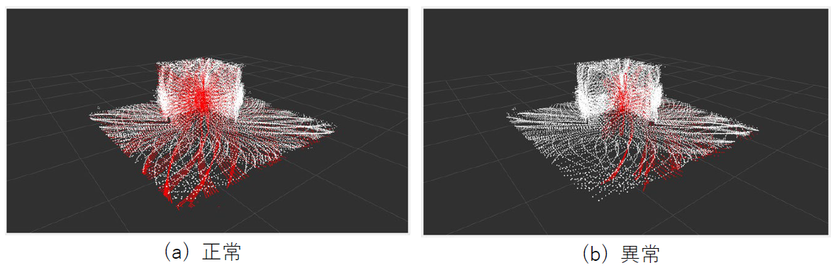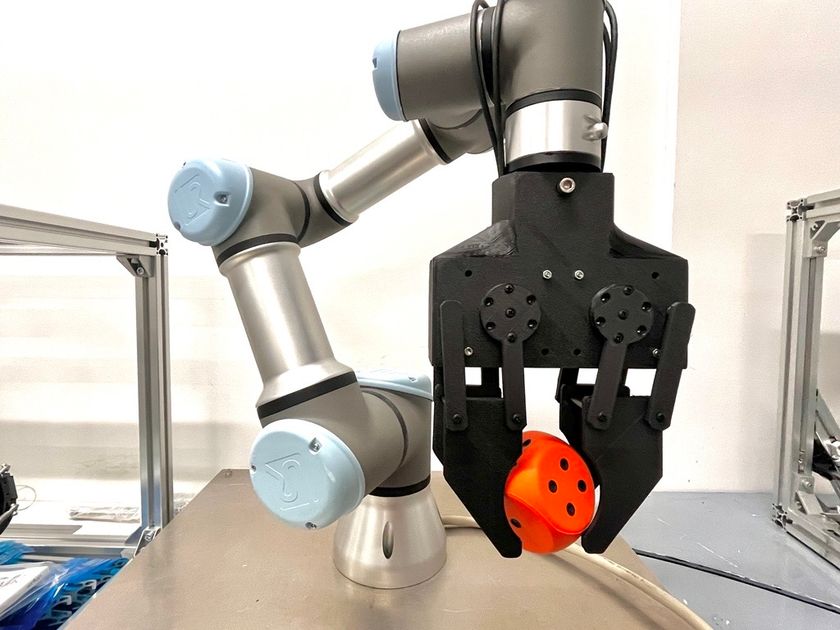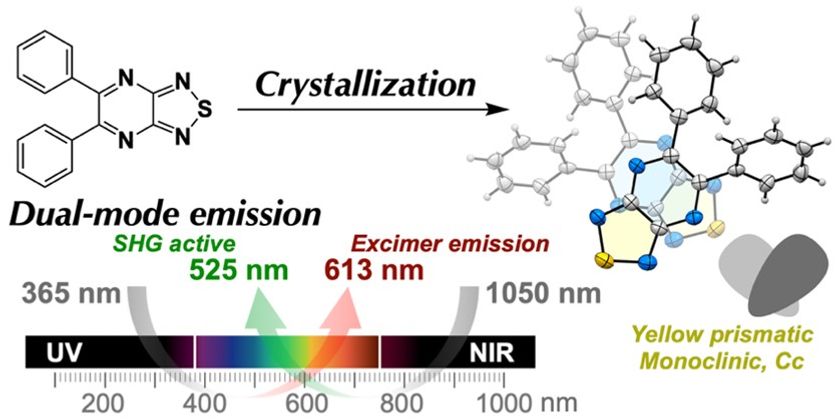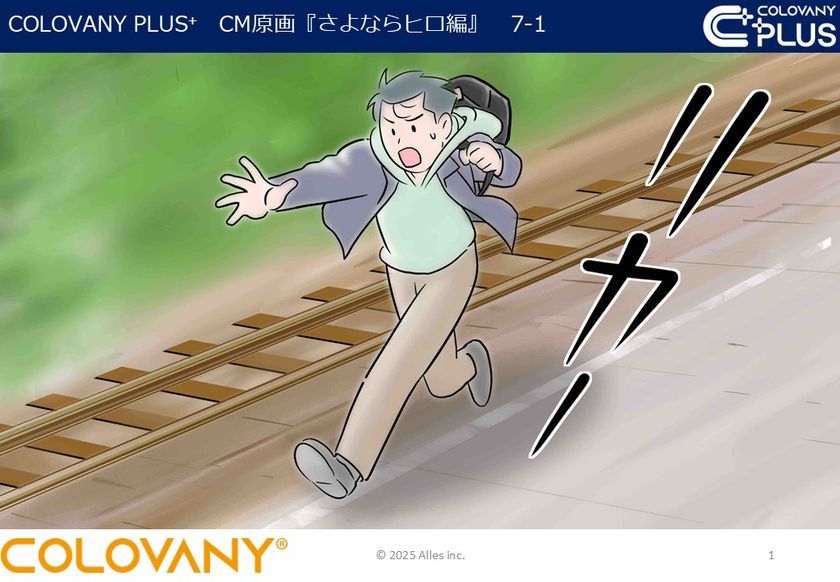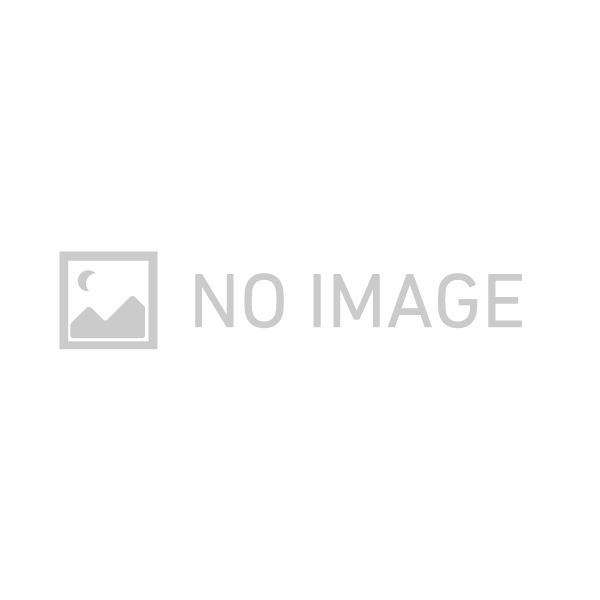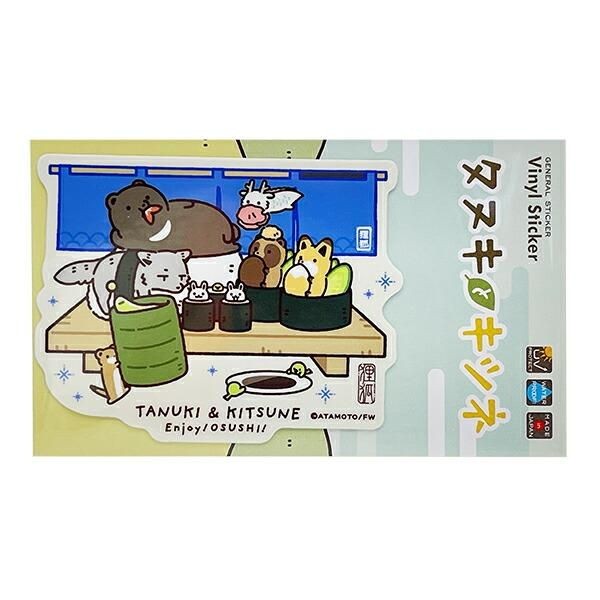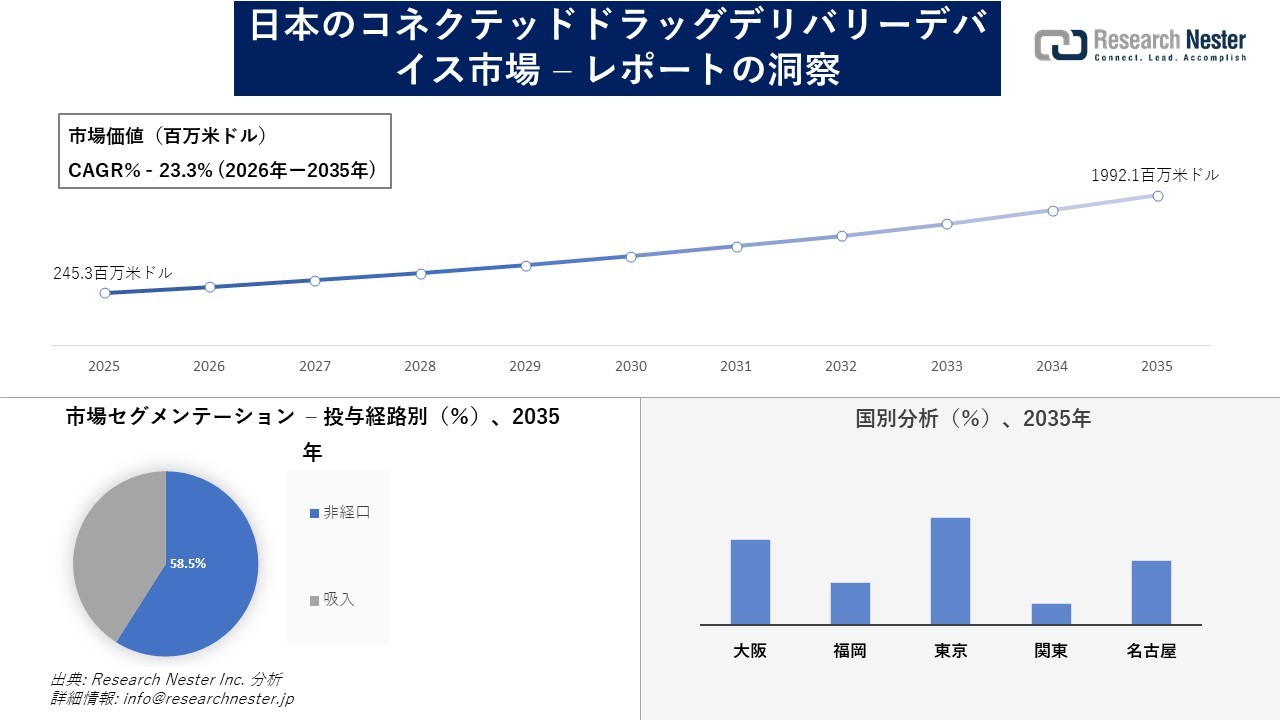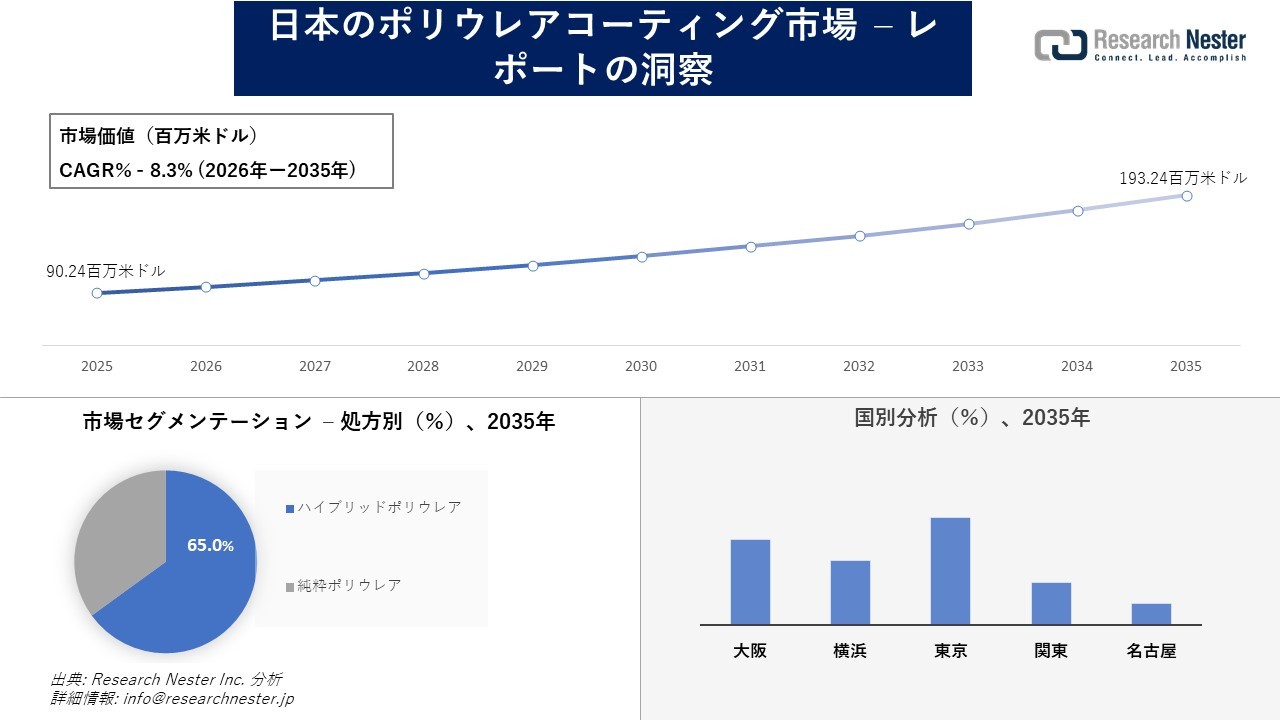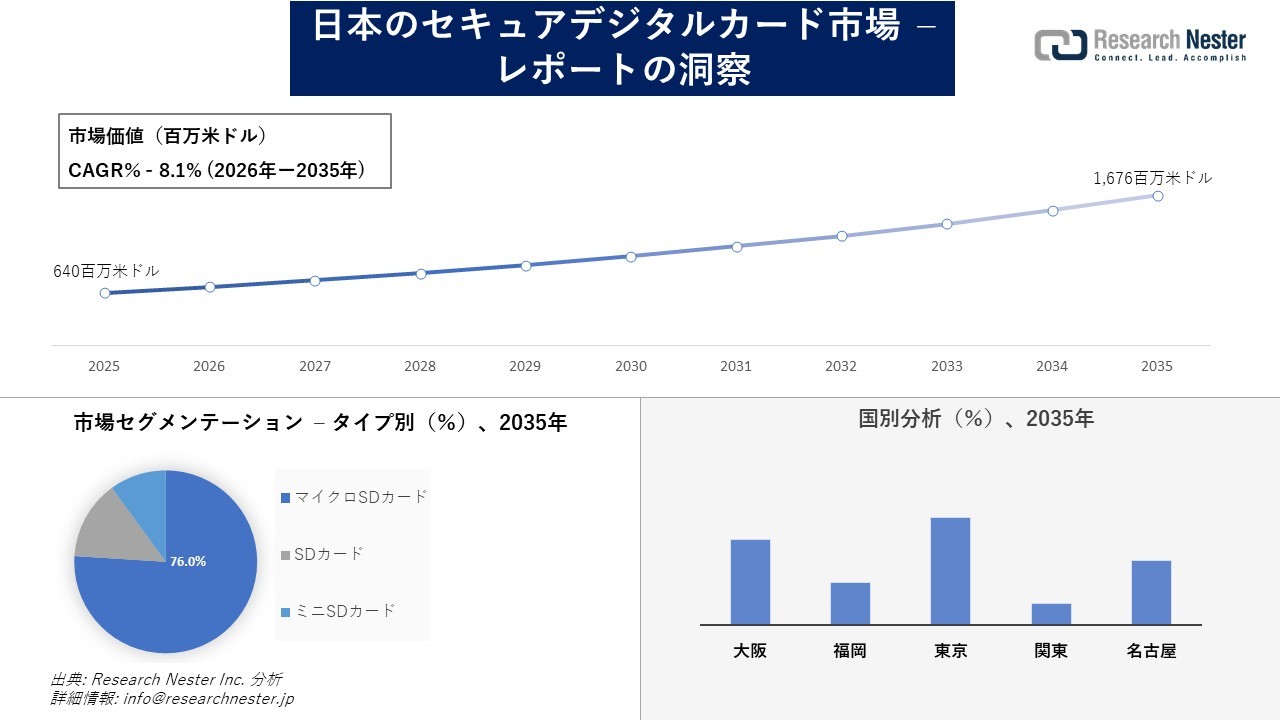石垣島の小学校で理科実験授業 学生団体が島の未来を担う子どもたちに環境教育 ~赤土流出がサンゴ礁に与える影響を学ぶ~
企業動向
2016年2月22日 14:00芝浦工業大学(東京都江東区豊洲、学長:村上雅人)の学生プロジェクト『石垣島を元気にするプロジェクト』は、2月25日、26日に沖縄県石垣島の白保小学校と真喜良小学校を訪れ、サンゴ礁の死滅・白化の原因となる“農地からの赤土流出”の防止を目的とした、環境教育としての理科実験授業を行います。
これからの石垣島を担う小学生に、赤土対策をした場合としない場合の違いを実験によって直接体験してもらうことで、世界的にも広大なサンゴ礁保存への意識を醸成することを目指します。
■活動のねらい
・これからの石垣島を担う小学生に、農地からの赤土流出問題およびサンゴ礁保全への興味関心、問題意識を持ってもらう
・島民生活の根幹である農業に起因する赤土流出問題を、島民の自発的な環境保全活動で改善していけるようにする
■授業の実施概要
・白保小学校
対象:4年生(20名)
日時:2016年2月25日(木)8:40~
・真喜良小学校
対象:5年生(50名)
日時:2016年2月26日(金)13:40~
<場所>
理科室
<内容>
授業:プレゼン方式で、赤土とサンゴの関連性や、島のサンゴの現状を理解してもらう
実験:赤土流出対策実験を班ごとに行う。各班、数種類の材料を使いタッパー内の赤土に工夫をして、その流出度合を観察する
発表:結果の違いについて、班ごとに成果を発表。
講評:学生が実験結果についてのコメントをし、実際に畑で行われている赤土流出対策の紹介も行い、より理解を深めてもらう
<昨年の小学校での授業の様子>
https://www.atpress.ne.jp/releases/91692/img_1.jpg
https://www.atpress.ne.jp/releases/91692/img_2.jpg
■赤土流出がサンゴに影響するメカニズム
スコールなどの強い雨により、島から海へ赤土が流出します。これにより、光合成から多くの栄養を得ているサンゴは土が被さることで光を受けられず、栄養を摂取することが出来なくなり死滅し、白化してしまいます。特に赤土の流出量が多いとされているのが石垣島の農地であり、作物が植わっていない裸地の時期の流出量が多くなります。
本プロジェクトでは、農作物を育てない時期にヒマワリを植えて根を張らせ、スコールで赤土が海まで流出しないよう取り組んでいます。
■「石垣島を元気にするプロジェクト」とは
石垣島を対象に、サンゴ礁保全活動を学生17名のグループが自主的に行っています。活動12年目となる本プロジェクトは、国や県から十分な補助金が得られないなどの理由で赤土流出対策がされていない農地からの耕土流出に着目し、島民による自発的なサンゴ礁保全が行われていくことを最終目標として活動しています。
上記活動のほか、現地の高校生や石垣市観光協会と協力し、島民のサンゴ礁保全の意識啓発を目的とした「サンゴウィークイベント」でも活動を行っており、2016年2月28日(日)には「サンゴを救え!ヒマワリ大作戦!!第二弾」を実施し、赤土流出がサンゴにおよぼす影響を紙芝居で説明した後、赤土流出対策として実際にヒマワリ緑肥のための種まきを参加者と行います。