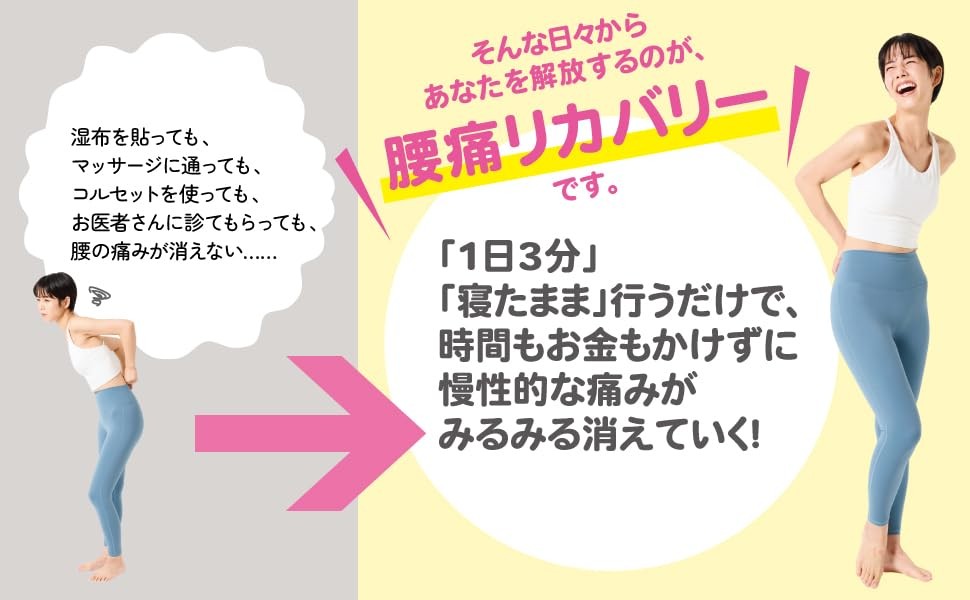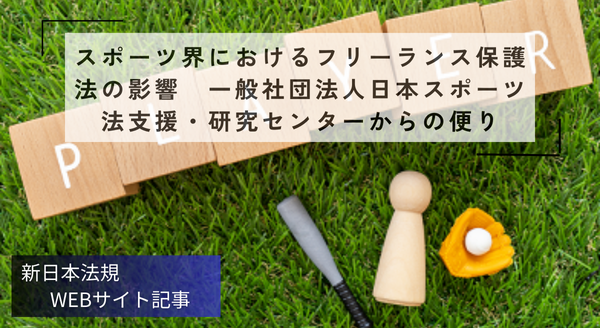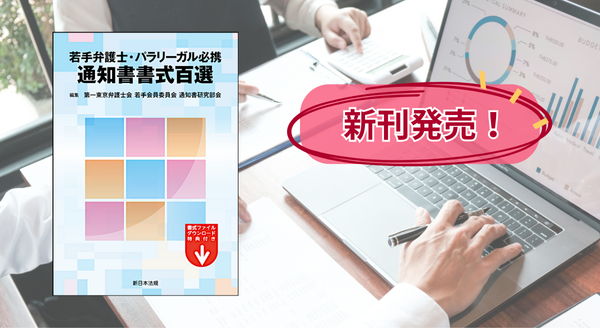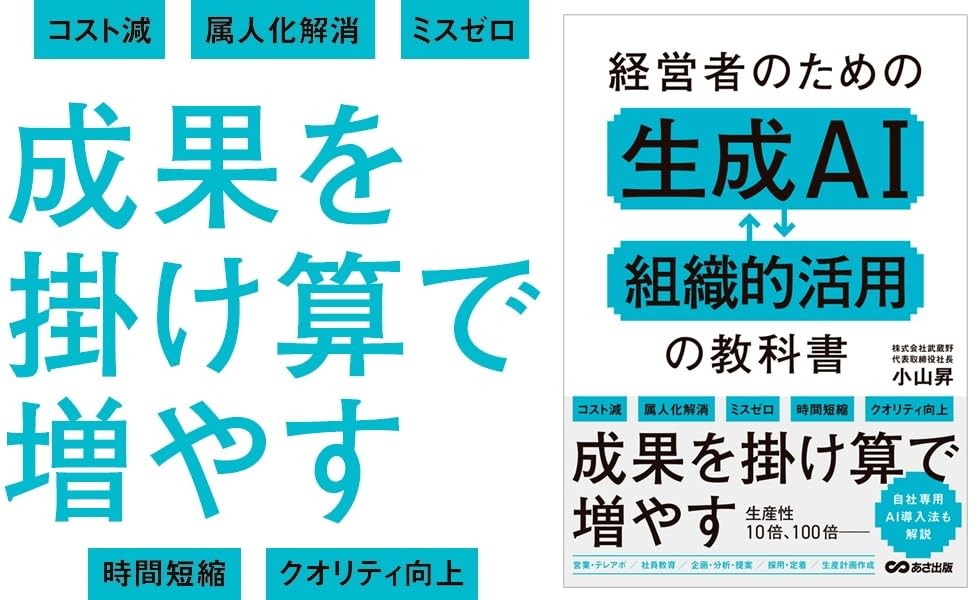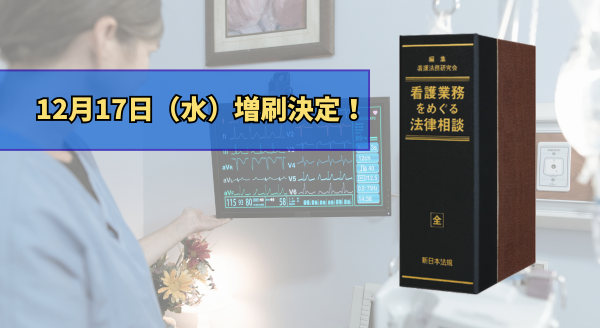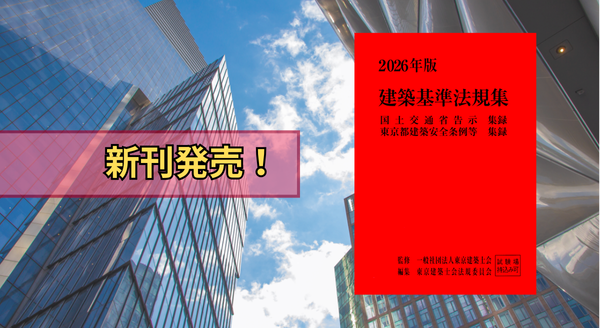発達障害・グレーゾーン、ひきこもり……子どもの生きる力を育む間取りとは?

クボデラ株式会社の窪寺伸浩社長は、発達障害・グレーゾーン、引きこもりなど、社会のなかで生きづらさを感じる子どもに対して、住環境からのアプローチで生きる力を育む方法を提案しています。
その理由は、「人間は環境の影響を受ける生き物ですが、人間はその環境を自らつくり変えることができるから」と言います。
窪寺社長の著書『間取りと素材で決まる 生きづらさを抱える子どもの生きる力を育む住まいとリフォーム』http://www.asa21.com/book/b599183.htmlより、間取りの工夫を2つ紹介します。
人間関係をつくるキッチン
家族の集まる場所はどこでしょうか? 昭和時代の漫画の『サザエさん』にも、ずっとあとの世代であるはずの『ちびまる子ちゃん』にも、現代住宅にあるキッチンも、ダイニングもありません。
キッチンの日本語は、何でしょうか。台所でしょうか。
ではダイニングは、何でしょうか。キッチン・台所に隣接しているから、本来は食堂なのでしょうが、「茶の間」的用素もあります。
このキッチン・ダイニングを改善して、家族の人間関係を再構築することを考えてみます。
まず、キッチンを、対面式に変えます。
換気などを考えれば、窓側にキッチンがあった方がよいですが、家族との関係性を考えれば、対面式もよいでしょう。

家事をしながら、家族の姿を見ることができる。
家事をしながら、家族と会話ができる。
人間関係をつくる上で、対面式キッチンは有効です。
さらに、リビングにいる家族に、あるいは、いなくても、呼びかけて、家事の手伝いをしてもらうといいでしょう。
一緒に家事をする。一見単純そうに見えますが、料理の手伝いをしてもらうだけでも、家族との共同作業になります。
なにも子どもに、一つの料理を完成させることを求めなくてもいいのです。
玉ねぎの皮むきでも、ニンニクの皮むきでもいいのです。
そして次は、野菜を切ること。次は味つけをすること。味見をすること。
料理づくりをするキッチンのなかで、会話がはずむはずです。
そのためには、一人で窮屈になるキッチンスペースではなく、家族と一緒にいられるスペースがあればいいでしょう。
キッチンは、料理をつくったり、洗いものをしたりする作業スペースです。
だから、さまざまな食材や器材を収納するスペースが求められます。
それゆえに作業スペースを圧迫するような収納スペースがありますが、これらを一カ所にまとめて、キッチンの背面にマグネットで貼れるようにして、作業の必要に応じて、背面に置いて作業する方法もあります。
これは、新築にもリフォームにも使えるアイデアです。
ひきこもりが解消される「家庭内引っ越し」
家の中での引っ越しを実践することによって、ひきこもりが解消された例があります。私の友人で、共に住環境を研究する工務店の社長から聞いた話です。
以下、友人の語りです。
お子さんが、少し気弱で、家にひきこもりがちでした。
そのお母さんから相談をうけて、そのお宅を訪ねることにしました。
子ども部屋は北向きで、昼でも電気をつけていないと薄暗い感じがしました。
私は、お子さんのひきこもりの原因が、この北窓のある部屋にある、と考えました。
「お母さん、引っ越ししませんか」と言うと、お母さんは「何を言うんですか、最近、この家を買ったばかりなのに、引っ越しなんて」と不満顔です。
「いやいや、家の引っ越しではありません。部屋の引っ越しですよ」といって、お宅をよくよく拝見させてもらうと、東南の角部屋が、単なる物置きになっているのに気づきました。一番いい場所が、単なる収納スペースになっているとは。
「朝日は生命を感じるもの。たんすや本棚に朝の光をあてても何も変わらない」と心のなかでつぶやきました。
東窓の部屋にあった家具などを北窓の部屋に移動して、子ども部屋を東窓の部屋に引っ越してもらいました。
南面にも窓をつくり、内装は木を使いました。
部屋の引っ越しをしてみると、いつも寝坊していた子どもが、朝早く目覚めるようになりました。
東窓の部屋は、朝日が入る部屋です。そして南窓は昼の光の入る部屋です。
太陽の光が、東窓から「朝だよ。朝だよ」と声掛けしてくれています。
そして昼になると、南窓から太陽が「昼だよ。昼だよ」と声を掛けてくれる。

子どもは、太陽の光の中で、規則正しく起きることから、徐々に、生活習慣を改めていって、ひきこもりから脱していったのです。
私はやはり、環境が人間を変えることを、つくづく思いましたし、また人間は環境を選べるし、環境をつくり、変える力があるのだと思ったのです。
これは私の友人から聞いた生の話です。
家庭内引っ越し、つまり環境を整えていくことの重要性が、おわかりいただけたはずです。
著者プロフィール
窪寺 伸浩(くぼでら・のぶひろ)

クボデラ株式会社代表取締役。
昭和36年東京都生まれ。東洋大学文学部卒。昭和21年創業の老舗木材問屋の三男として生まれ、台湾、中国等からの社寺用の特殊材の輸入卸を行う。また、全国の志ある工務店、木材業者、設計士等によってつくられた「幸福(しあわせ)を生む住まいづくり」を提唱し、実践する環境研究グループ「ホーミースタディグループ」の中核メンバーでもある。東京都神社庁御用達。東京都神棚神具事業協同組合理事長。同社マルトミホーム事業部では、自然素材・無垢材にこだわった家づくりを40年にわたって行っている。
書籍情報

タイトル:間取りと素材で決まる 生きづらさを抱える子の生きる力を育む住まいとリフォーム
著者:窪寺伸浩
ページ数:200ページ
価格:1,650円(10%税込)
発行日:2022年3月11日
ISBN:978-4-86667-370-7
http://www.asa21.com/book/b599183.html
amazon:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866673702/asapublcoltd-22/
楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/17008957/?l-id=search-c-item-text-01
目次
第1章 住まいを生きる力を育む場に
第2章 生きる力を育む間取り
第3章 住まいのあるべき姿
第4章 生きる力を育む素材選び
第5章 住まいづくりをどのように進めるか