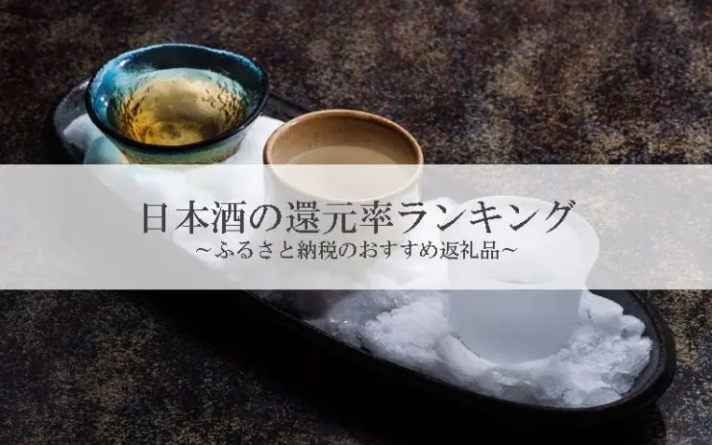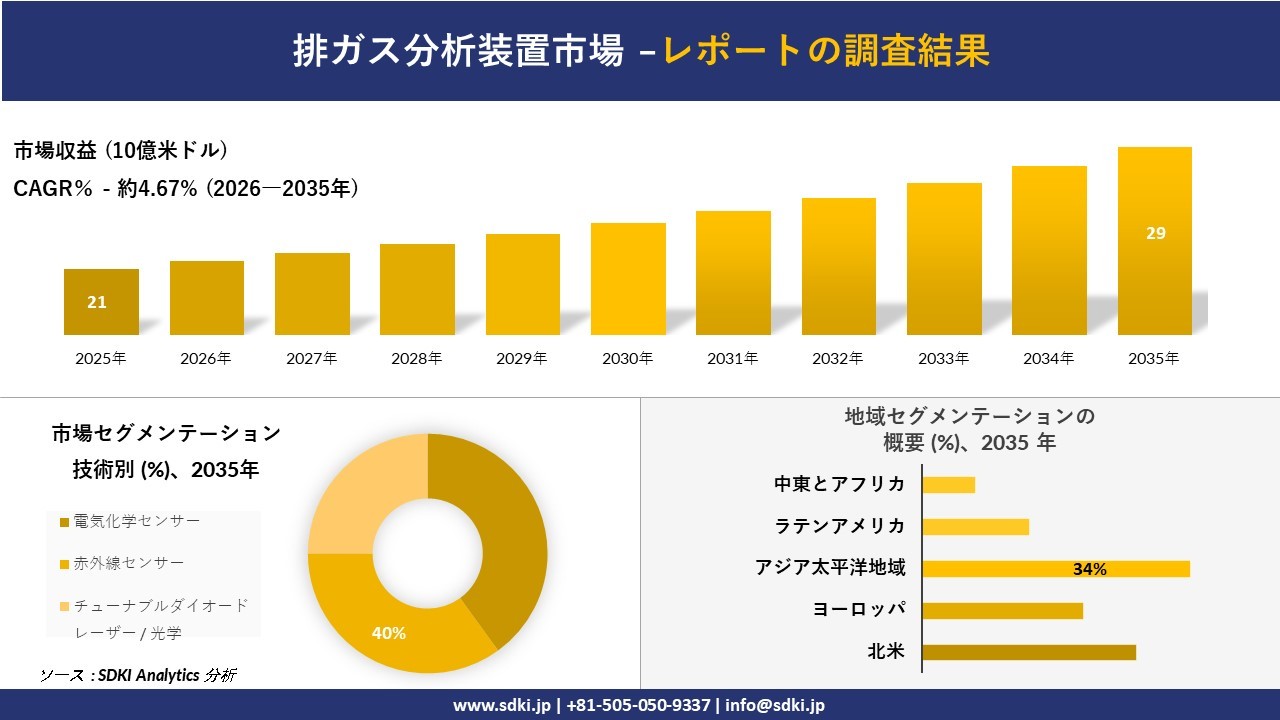【地域別の葬儀文化】都市部と地方では葬儀形式や費用に差異が出る結果に
株式会社ディライト(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:高橋 亮)は、喪主を務めたことのある男女を対象に、「地域ごとの葬儀の風習の違い」に関する調査を実施しました。
日本では、地域ごとに葬儀の形式や風習が大きく異なり、それぞれに特有の文化が存在します。
都市部と地方では葬儀の進め方や参列者数、費用などにどのような違いがあるのでしょうか。
また、地域特有の風習にはどのようなものがあるのでしょうか。
そこで今回、『葬儀の口コミ』(https://soogi.jp)を運営する株式会社ディライト(https://delight.co.jp/)は、葬儀に行ったことがある、または参列したことがある20~70代の男女を対象に「地域ごとの葬儀の風習の違い」に関する調査を行いました。
調査概要:「地域ごとの葬儀の風習の違い」に関する調査
【調査期間】2024年9月18日(水)~2024年9月20日(木)
【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査
【調査人数】1,004人
【調査対象】調査回答時に葬儀に行ったことがある、または参列したことがある20~70代の男女と回答したモニター
【調査元】株式会社ディライト(https://delight.co.jp/)
【モニター提供元】PRIZMAリサーチ
※調査結果の全容は下記サイトでご紹介しております。
評判のいい葬儀社に依頼できる口コミサイト『葬儀の口コミ』
【https://soogi.jp/news/1814】
【本リリースの引用・転載時のお願い】
・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。
『葬儀の口コミ』の調査によると...
リンク先<https://soogi.jp/news/1814>
首都圏・関西で「新聞の訃報欄」はほとんど使われない
まずはじめに、知人の葬儀をどのように知ったか伺いました。


「知人の葬儀があることを知る経路として、経験したことがあるものを全て選んでください(複数回答可)」と質問したところ、東北地方・北陸地方・首都圏・関西地方・九州地方で以下のような回答になりました。
【東北地方】
・『親族からの連絡(84.5%)』
・『友人からの連絡(57.5%)』
・『新聞の訃報掲載欄(34.5%)』
【北陸地方】
・『親族からの連絡(84.0%)』
・『友人からの連絡(58.0%)』
・『新聞の訃報掲載欄(34.0%)』
【首都圏】
・『親族からの連絡(81.2%)』
・『友人からの連絡(60.9%)』
・『郵送による通知(7.9%)』
【関西地方】
・『親族からの連絡(84.6%)』
・『友人からの連絡(60.2%)』
・『郵送による通知(4.0%)』
【九州地方】
・『親族からの連絡(87.1%)』
・『友人からの連絡(66.2%)』
・『新聞の訃報掲載欄(16.4%)』
東北地方・北陸地方・九州地方では新聞の訃報掲載欄の利用率が比較的高くなっており、新聞が地域社会の重要な情報源として機能していることが伺えます。
首都圏では新聞の訃報掲載欄が4%にとどまったこと、関西では上位に入ってこなかったことから、新聞購読率の低下やコミュニティの規模と結びつきの違いがみられる結果となりました。

続いて、「直近で経験した葬儀はどのような形式でしたか?」と質問したところ、東北地方・北陸地方・首都圏・関西地方・九州地方で以下のような回答になりました。
【東北地方】
・『一般葬(参列者を限定せず通夜と告別式を行う従来型の葬儀)(57.5%)』
・『家族葬(近親者のみで行う小規模な葬儀)(37.0%)』
【北陸地方】
・『一般葬(参列者を限定せず通夜と告別式を行う従来型の葬儀)(43.6%)』
・『家族葬(近親者のみで行う小規模な葬儀)(46.0%)』
【首都圏】
・『一般葬(参列者を限定せず通夜と告別式を行う従来型の葬儀)(42.3%)』
・『家族葬(近親者のみで行う小規模な葬儀)(52.2%)』
【関西地方】
・『一般葬(参列者を限定せず通夜と告別式を行う従来型の葬儀)(53.2%)』
・『家族葬(近親者のみで行う小規模な葬儀)(43.3%)』
【九州地方】
・『一般葬(参列者を限定せず通夜と告別式を行う従来型の葬儀)(57.5%)』
・『家族葬(近親者のみで行う小規模な葬儀)(37.0%)』
首都圏は家族葬の割合が半数以上となり、都市化に伴う生活様式の変化、核家族化、地域コミュニティの希薄化などが要因として考えられます。
また東北や九州などの地方では、地域社会の結びつきが強いため、一般葬を選択する要因の一つになっていることが示唆されました。
東北地方では火葬後に葬儀が行われる割合が3割以上!首都圏では葬儀まで1週間以上かかることも
葬儀の流れは、地方によって差があるのでしょうか。

「葬儀の流れはどちらでしたか?」と質問したところ、東北地方とそれ以外の全国で差異がみられる結果になりました。
【全国】
・『通夜や葬儀の後にお骨の火葬が行われた(87.7%)』
・『お骨の火葬が行われた後で通夜や葬儀が行われた(12.3%)』
【東北地方】
・『通夜や葬儀の後にお骨の火葬が行われた(64.0%)』
・『お骨の火葬が行われた後で通夜や葬儀が行われた(36.0%)』
東北地方では、火葬を先に行う「前火葬」の割合が3割以上と、全国平均の約1割を大きく上回っています。東北地方では火葬を先に行う風習が根強く残っているようです。
さらに、葬儀にかかる日数についても伺いました。

「亡くなってから葬儀を行うまでの日数を教えてください」と質問したところ、東北地方・北陸地方・首都圏・関西地方・九州地方で以下のような回答になりました。
【東北地方】
・『1日~3日(54.0%)』
・『4日~6日(33.0%)』
・『7日~(13.0%)』
【北陸地方】
・『1日~3日(81.0%)』
・『4日~6日(17.5%)』
・『7日~(1.5%)』
【首都圏】
・『1日~3日(50.5%)』
・『4日~6日(31.7%)』
・『7日~(17.8%)』
【関西地方】
・『1日~3日(85.0%)』
・『4日~6日(11.5%)』
・『7日~(3.5%)』
【九州地方】
・『1日~3日(95.0%)』
・『4日~6日(3.5%)』
・『7日~(1.5%)』
首都圏では7日以上と回答した方の割合が最も多くなっています。これは人口密度が高いために、葬儀場や火葬場の予約の混雑などが大きな要因になっているのではないでしょうか。
他の地域、特に九州地方では「1日〜3日」で葬儀が行われるケースが9割以上と、亡くなってから比較的日数を置かずに葬儀ができる傾向が見られます。
首都圏と関西地方では費用を抑えた葬儀が多い傾向に
ここまで葬儀の形式や流れの中で地域差がみられる結果となりましたが、費用に関しても地域によって違いはあるのか質問しました。


葬儀を行ったことがあると回答した人のみに、「葬儀を行う際の費用はどれくらいでしたか?」と質問したところ、東北地方・北陸地方・首都圏・関西地方・九州地方で以下のような回答になりました。
【東北地方】
・『30万円未満(7.3%)』
・『30万円~90万円未満(27.4%)』
・『90万円~150万円未満(37.9%)』
・『150万円~210万円未満(16.1%)』
・『210万円~270万円未満(3.2%)』
・『270万円以上(8.1%)』
【北陸地方】
・『30万円未満(8.0%)』
・『30万円~90万円未満(19.2%)』
・『90万円~150万円未満(40.0%)』
・『150万円~210万円未満(12.8%)』
・『210万円~270万円未満(11.2%)』
・『270万円以上(8.8%)』
【首都圏】
・『30万円未満(15.7%)』
・『30万円~90万円未満(17.9%)』
・『90万円~150万円未満(44.0%)』
・『150万円~210万円未満(14.2%)』
・『210万円~270万円未満(2.2%)』
・『270万円以上(6.0%)』
【関西地方】
・『30万円未満(11.3%)』
・『30万円~90万円未満(31.0%)』
・『90万円~150万円未満(33.8%)』
・『150万円~210万円未満(15.5%)』
・『210万円~270万円未満(3.5%)』
・『270万円以上(4.9%)』
【九州地方】
・『30万円未満(15.5%)』
・『30万円~90万円未満(19.4%)』
・『90万円~150万円未満(35.7%)』
・『150万円~210万円未満(17.1%)』
・『210万円~270万円未満(4.7%)』
・『270万円以上(7.8%)』
唯一、首都圏でのみ30万円未満の低価格帯の割合が3番目に高くなっており、関西地方では「30万円未満」と「30万円~90万円未満」を合わせた90万円未満が4割以上と、比較的低コストで行われていることを示しています。
人口の多い地域においては、小規模な葬儀や費用をある程度抑えた傾向が強いことが示唆されました。
一方、首都圏・関西地方以外の「東北地方」「北陸地方」「九州地方」では、150万円以上の費用をかけて実施している割合は27%以上と高くなっているため、伝統的な葬儀形式が好まれている可能性があります。
では葬儀を行ったことがある方は、どのように葬儀社や葬儀場所を選んでいたのでしょうか?
記事の続きは下記サイトでご紹介しております。
評判のいい葬儀社に依頼できる口コミサイト『葬儀の口コミ』
【https://soogi.jp/news/1814】
地域の葬儀事情に詳しい葬儀社を選ぶなら『葬儀の口コミ』

今回、「地域ごとの葬儀の風習の違い」に関する調査を実施した株式会社ディライト(https://delight.co.jp/)は、『葬儀の口コミ』(https://soogi.jp/)を運営しています。
調査でも見られた通り地域によって葬儀事情は様々。そのため地域の葬儀事情に詳しい葬儀社に依頼するのが安心です。
「葬儀の口コミ」では、地域ごとに葬儀社を検索することができます。
最大の特長は、情報の種類と量、そして手軽さにあります。会員登録などの必要はなく手間をかけずにすぐに情報収集ができます。急に葬儀社を選ばなければならない場面においても安心です。
特に葬儀においては、事前の準備や情報収集が困難な場合が多いです。
「葬儀の口コミ」を見ればそうした状況においても信頼性の高い情報をタイムリーに見ることができます。
葬儀の口コミ』が選ばれる理由
・全国24時間365日 対応可能
24時間365日対応。どんな時でも葬儀のご相談・ご依頼ができます。
・葬儀業界No.1の口コミ掲載数
掲載葬儀社12,576社、口コミ掲載数51,773件からあなたの条件に合った葬儀社を探せます。
・葬儀社と直接話せる
オペレーターではなく、葬儀社と直接連絡でき、葬儀の流れや不安な点をくわしく相談できます。
・完全無料で使える
お見積り・ご相談はすべて完全無料。会員登録不要。安心してお使いいただけます。
会社名 :株式会社ディライト
設立 :2007年10月1日
本社所在地:東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F
代表者 :代表取締役 高橋 亮
資本金 :50,000,000円(2023年1月31日現在)
URL :https://delight.co.jp
サービス▼
『葬儀の口コミ』:https://soogi.jp
『葬儀のウェブ担当』:https://sougi-webtan.com
『お墓の口コミ』:https://oohaka.jp
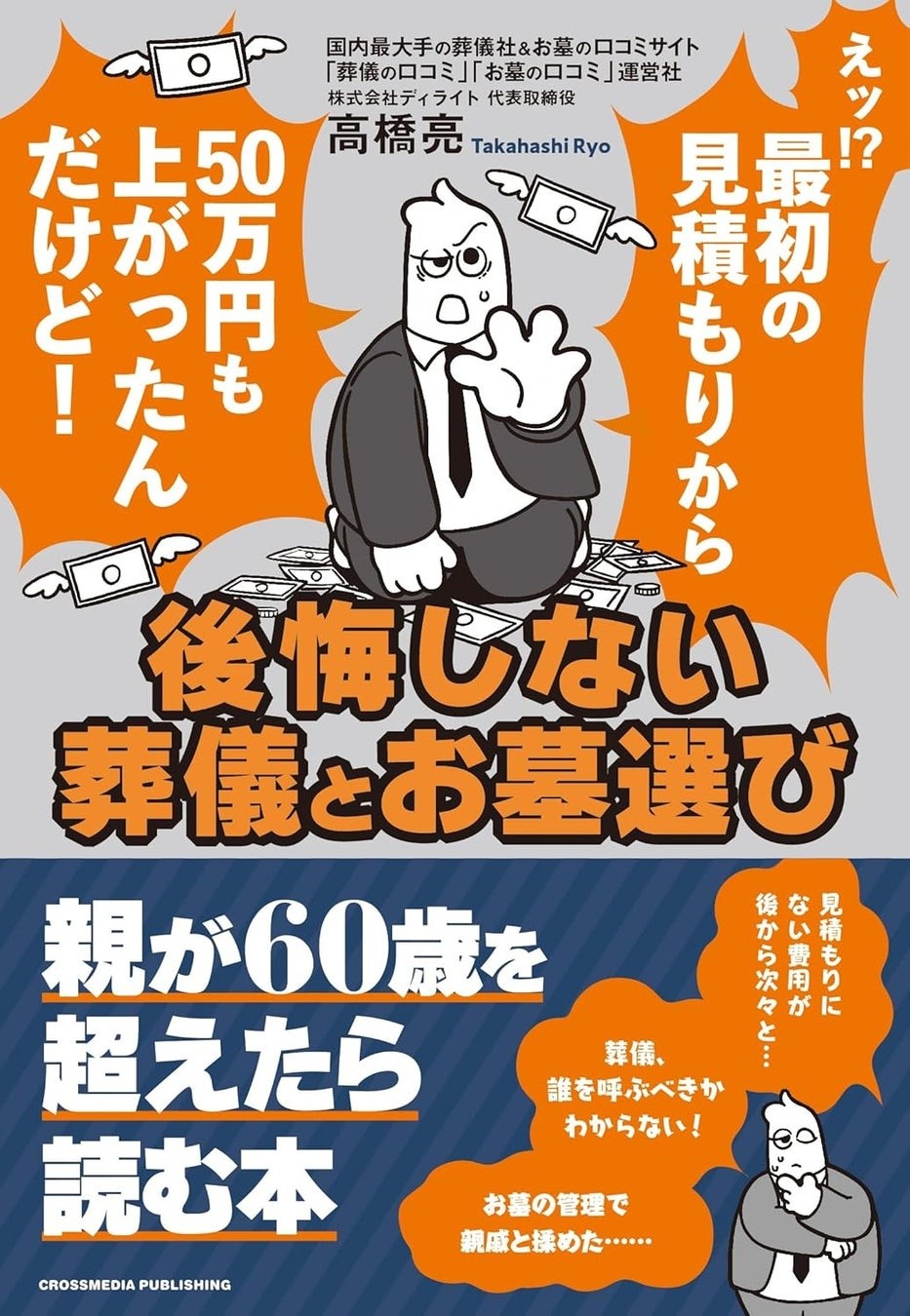




![大流行中のシル活にぴったり!7月販売予定のサンリオのキュートなシールに夢中![予約受付開始]](https://newscast.jp/attachments/ITkaVmK3s13HO2pIThan.jpg)