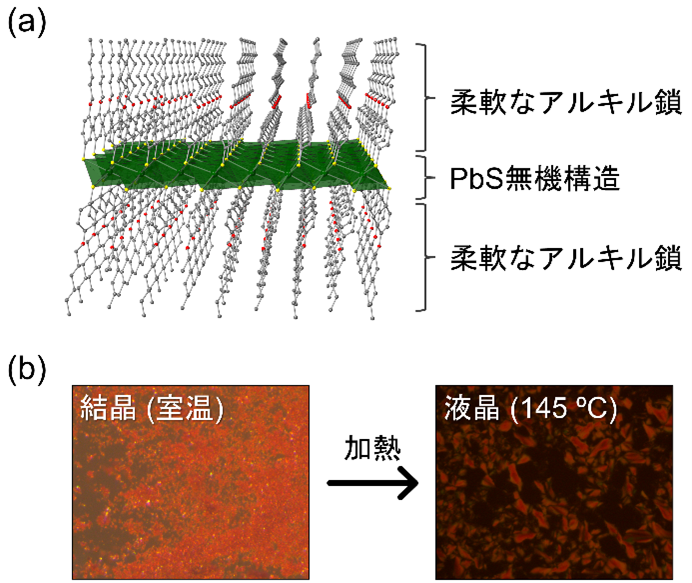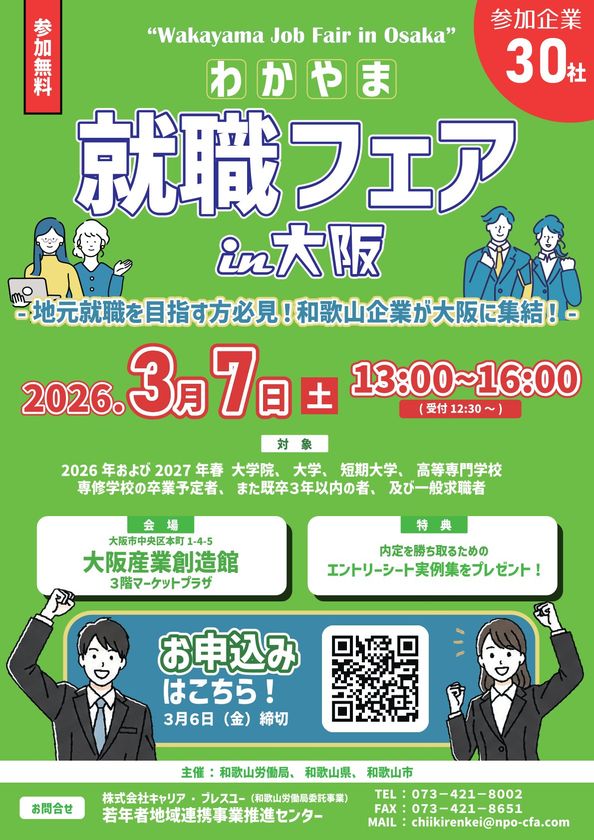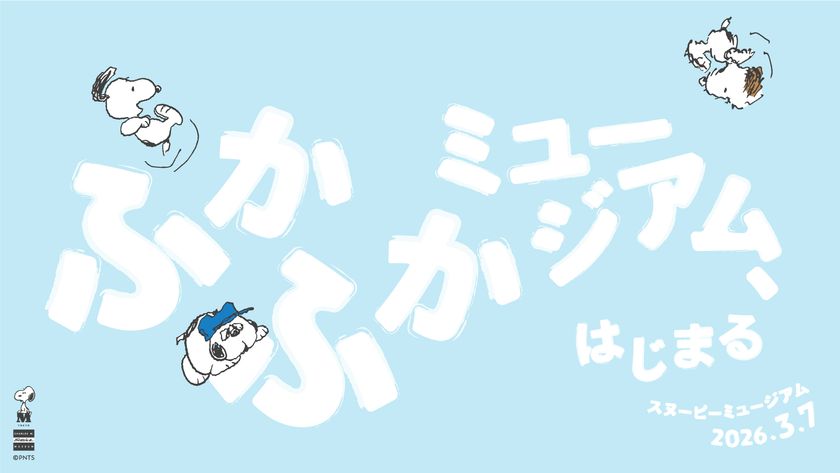「無形文化財×デジタル・ヒューマニティーズ」をテーマにシンポジウム 文化財の保存と活用を探り、文化資源学の未来を考える

近畿大学文芸学部文化・歴史学科と近畿大学民俗学研究所(ともに大阪府東大阪市)は、令和7年(2025年)2月8日(土)、東大阪キャンパスにて、シンポジウム「文化資源学のこれまでとこれから」を開催します。「無形文化財×デジタル・ヒューマニティーズ※」をテーマに、3名の識者による発表とパネルディスカッションを行い、今後の文化資源の保存と活用について考えます。
※人文学(歴史、文学、哲学など)に関する問題を、コンピュータ技術やデータ分析の手法を使って解決しようとすること。
【本件のポイント】
●デジタル技術を活用した文化財保存について考えるシンポジウムを開催
●3名の識者の発表とパネルディスカッションを通じて文化資源保存と活用について意見交換
●デジタル・ヒューマニティーズを通じて文化資源学の可能性を探る
【本件の内容】
令和2年(2020年)以降に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、文化および文化資源をとりまく状況は大きく変わりしました。特に、祭祀・儀礼・習俗といった無形の文化は、以前から人口減少や技術革新にともなって存続の危機が言われていましたが、この機に取りやめられてしまったものがたくさんあります。その一方で、文化資源の掘起し・記録・活用をサポートしてくれるデジタル技術が飛躍的に進歩し、科学技術と人文学を掛け合わせた「デジタル・ヒューマニティーズ」が注目されています。
近畿大学文化・歴史学科と近畿大学民俗学研究所では、考古学・民俗学・地理学の分野を中心に文化資源学に取り組んできましたが、民俗学のようなフィールドワークに重きを置き、経験を拾い上げる学問では、デジタル・ヒューマニティーズの導入・活用の具体的な方法が見えずにいます。このシンポジウムでは、デジタル・ヒューマニティーズを実装した文化資源学の可能性を模索し、人の営みとつながる有形・無形の文化に焦点をあてることで、これからの文化資源学で何ができるのか考えることを目的にシンポジウムを開催します。
【開催概要】
日時 :令和7年(2025年)2月8日(土)14:00~17:00
場所 :近畿大学東大阪キャンパス BLOSSOM CAFE 3階多目的ホール
(大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分)
対象 :一般の方(定員100人、入場無料、要事前申込)
申込方法:下記フォームからお申込みください。
https://forms.gle/BwMK7PLB4gCDHnJr5
お問合せ:近畿大学文芸学部文化・歴史学科 担当:上田
TEL(06)6721-2332
E-mail :bunreki.project@lac.kindai.ac.jp
【スケジュール】
14:00 開会
14:10 基調報告「文化・歴史学科のはじまり:文化資源学がつなぐ」
近畿大学文芸学部文化・歴史学科 教授 髙宮いづみ
14:30 民俗文化財をめぐる課題~学術と運用の狭間から~
國學院大學観光まちづくり学部観光まちづくり学科 准教授 石垣悟氏
15:00 「デジタル・ヒューマニティーズの概要と事例紹介」
東京大学史料編纂所 助教 中村覚氏
15:45 パネルディスカッション「無形文化財×デジタル・ヒューマニティーズ」
國學院大學観光まちづくり学部観光まちづくり学科 准教授 石垣悟氏
東京大学史料編纂所 助教 中村覚氏
近畿大学文芸学部文化・歴史学科 教授 髙宮いづみ
近畿大学文芸学部文化・歴史学科 教授 藤井弘章
【講演者プロフィール】
石垣悟(いしがきさとる)氏
國學院大學観光まちづくり学部観光まちづくり学科 准教授
文化庁伝統文化課・文化財調査官(民俗文化財部門)を経て、令和6年(2024年)より現職。文化庁在職時は民俗文化財の保存調査に従事。近年は、民俗芸能を理解するための学習プログラムとWeb教材開発のためのプロジェクトを推進中。
中村覚(なかむらさとる)氏
東京大学史料編纂所 助教
くずし字OCRと編集距離を用いた写本・版本の比較支援システムの開発、荘園関係のデータベースや、LOD(Linked Open Data)などのデータベースを作成。LOD(Linked Open Data)の技術普及の促進を目指したオープンデータのコンテストとして開催されているLinked Open Data チャレンジJapan 2024で学術LOD賞を受賞。Linked Open Data チャレンジJapan 2023でデータ作成部門 優秀賞を受賞。
髙宮いづみ(たかみやいづみ)
近畿大学副学長、文芸学部文化・歴史学科 教授
専門はエジプト考古学。文化・歴史学科の教育の柱として文化資源学を導入し、その教育に携わる。
【関連リンク】
文芸学部 文化・歴史学科 副学長・教授 髙宮いづみ(タカミヤイヅミ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/1151-takamiya-izumi.html
文芸学部 文化・歴史学科 教授 藤井弘章(フジイヒロアキ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/1172-fujii-hiroaki.html