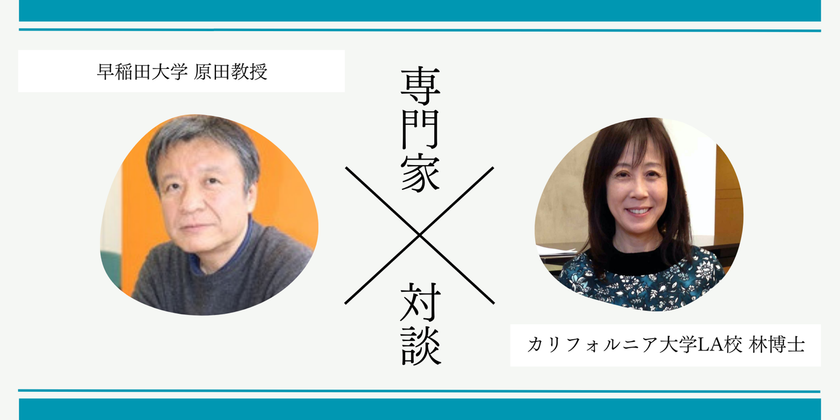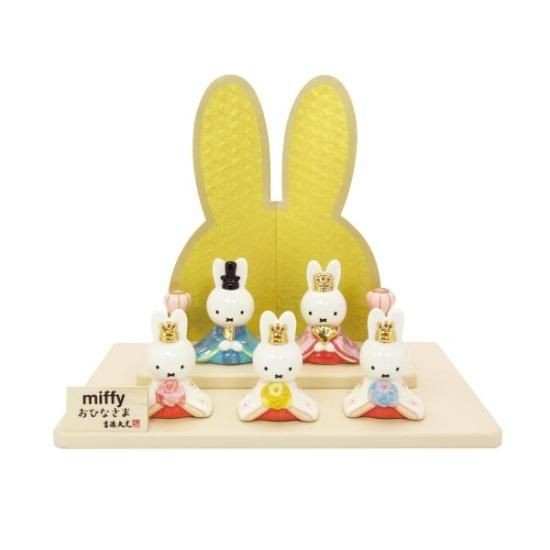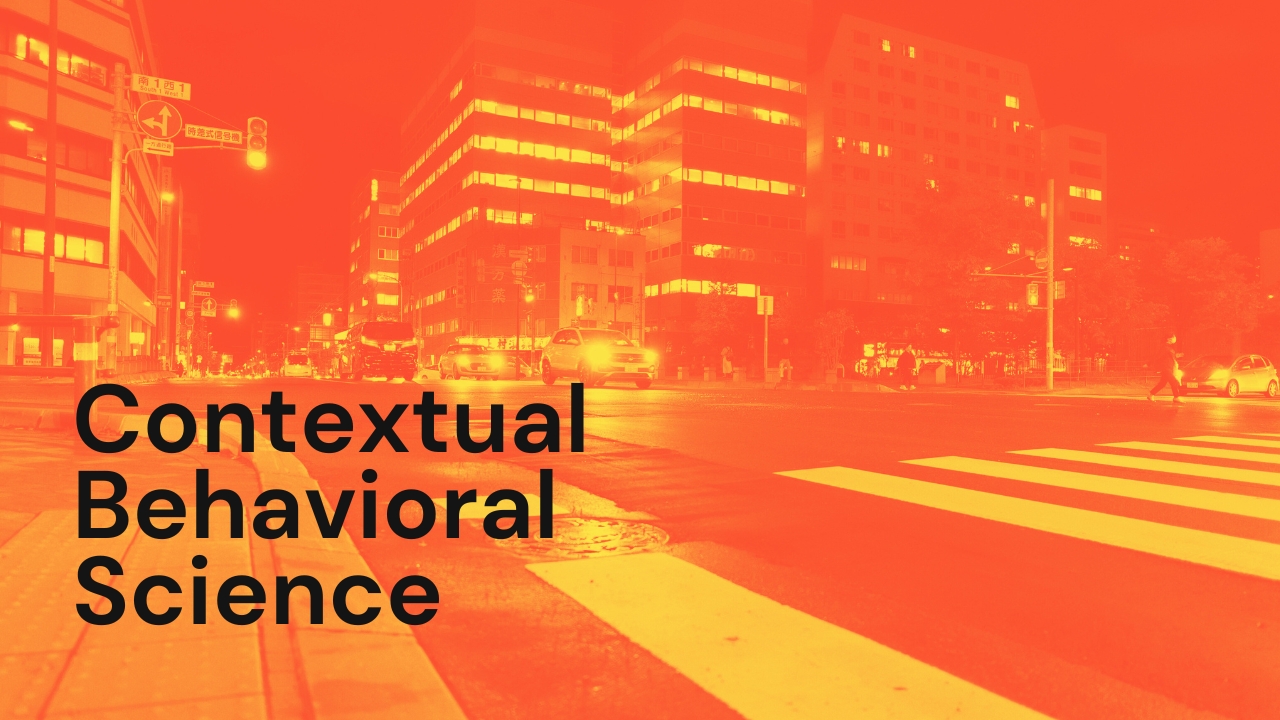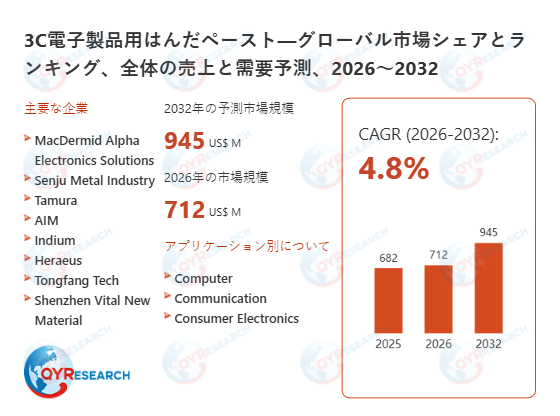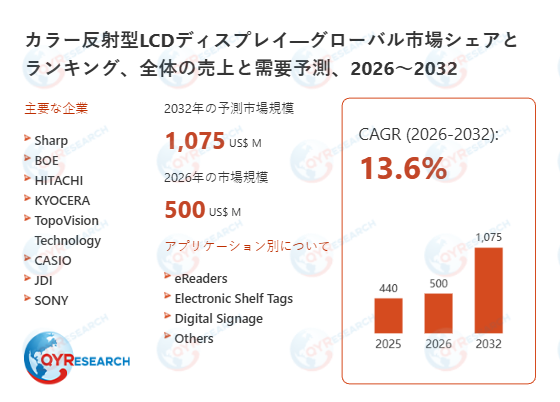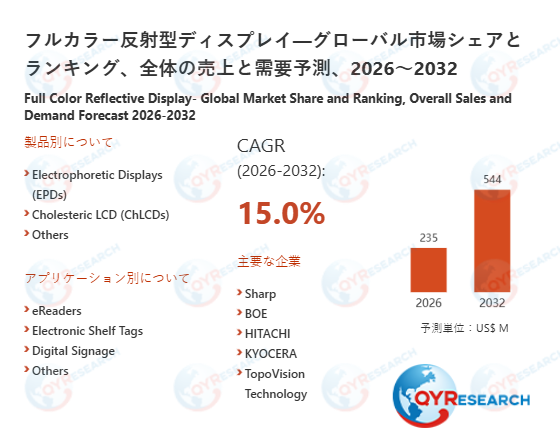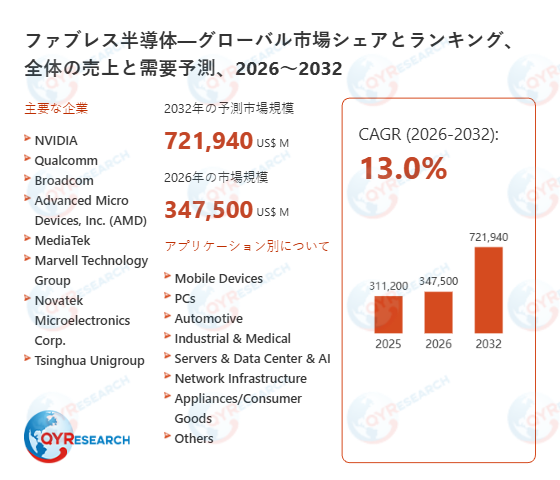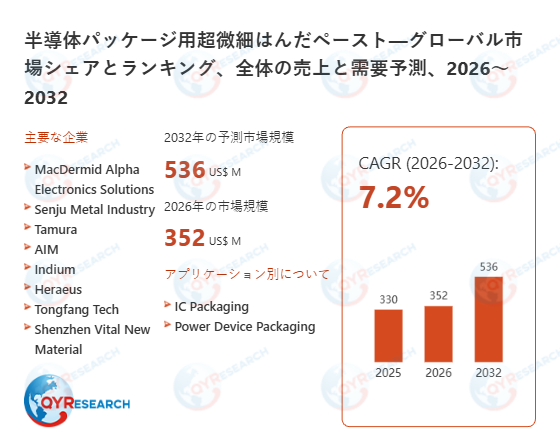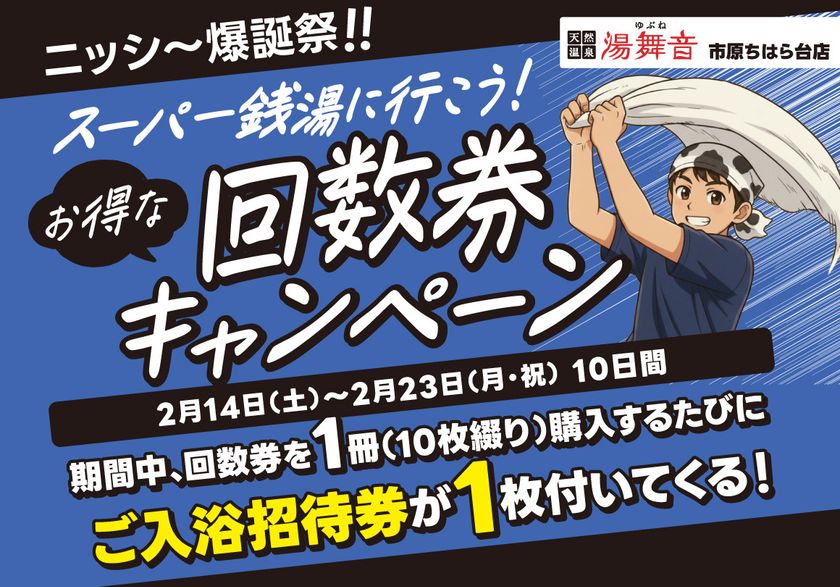AI時代、大学英語教育や教師に求められる「変革」とは 立命館大学の山中教授へのインタビュー記事を公開
ワールド・ファミリー バイリンガル サイエンス研究所(所在地:東京都新宿区、所長:大井 静雄、以下:IBS)では、グローバル化社会における幼児期からの英語教育の有効性や重要性に関する情報を、IBSのホームページ上で定期的に発信しています。
今回は、ChatGPTなどのテクノロジーを積極的に活用しながら大学英語教育の変革に取り組む山中 司教授(立命館大学)へのインタビュー記事を公開しました。

山中教授
<インタビュー記事のまとめ>
●テクノロジーは、自分の可能性を何倍にも増幅してくれるamplifier(アンプリファイア)として使わせる。そのためには、生徒にとって本当に意味のある課題を与えること、AIの使い方を自律的に考えさせる教育が大切。
●誰でもAIに教えてもらいながら自分がやりたいコミュニケーションができ、その経験を繰り返しながら英語を学べるようになった。従来「当たり前」とされてきた基礎積み上げ型の教育や評価のあり方を根本的に考え直す必要がある。
●教師は「英語を教える」から卒業し、教室という場の設計やガイドという役割にシフトしなければならない。生徒と一緒に学ぼうとする姿勢や人間力がこれまで以上に試される。
■「ズルをするため」ではなく、「発信能力を高めるため」にテクノロジーを使う
山中教授は、昨年9月から、学生たちが無制限に利用できる機械翻訳サービスを大学に導入。さらに、ChatGPTのほか、ライティングを剽窃(ひょうせつ)なども含めてチェックしてくれるTurnitin、文法や語彙、スタイルなどをチェックしてくれるe-rater(R)、VRなどのテクノロジーを英語の授業で活用しています。「自分なりのコミュニケーション・パターンや表現方法を見つけて自分をアピールしたりプロモーションしたりできるようになる、もっと本質的に発信力を高める教育をしたい」と話す山中教授。さらに、テクノロジーには、「ズルをするための使い方」と「自分の英語力を高めるための使い方」があるとのこと。「ズルをするために使う学生がいるからといって、使用を禁止することは安易で短絡的すぎると思います」と話します。
■AIを活用して、自分が伝えたいことをどんどんコミュニケーションすることで、英語を学習する
AIを活用することで、さまざまな学生が成功体験を得られる可能性があります。「ポイントは、AIの力を借りれば、自分が本当にやりたいコミュニケーションを誰でもできるようになったことなんです。自分が本当に伝えたい内容をどう言えばいいかAIに教えてもらいながらどんどんコミュニケーションして、その経験を何度も繰り返していけば、少しずつそこから学んで英語力が上がっていくと考えています。これは、英語教育においてとても革命的で、従来はあり得なかった学び方です。 -(中略)- 現実的に考えると、TOEICやIELTSなどのテストはなくならないでしょうし、受験者がテストで機械翻訳を使えるようにはならないと思います。何らかの形で生身の英語力を確かめようとするテストがある限り、『知識を学ぶ』ということはある程度必要なのかもしれません。そうすると、自分が本当にやりたいコミュニケーションをするためにAIをうまく使いながら『こうやって言えばいいんだ』と学んだり『自分で考えて言ってみよう』と挑戦したりしているうちに、10年、20年経っていつの間にか使える知識が自分にも備わっていた、という学び方は理想的だと思います。」と山中教授。
取材後記:AI使用を「前提」にすることで英語教育が変わる
AIは人間の能力を高めるamplifierである、という山本教授の考え方は、ニューヨーク市の公立学校がChatGPT使用禁止の方針を撤廃したことも考えると、今後の教育現場でますます重要になっていくと思われます。
生徒がAIを使うことを前提にして教育のあり方や教師の役割を考え直すことは、AI使用を禁止するよりも大変かもしれません。
しかし、AIをうまく活用すれば、知識や能力、時間などの制約によって諦めていたことに挑戦できるようになる、将来本当に必要となることを学んだり教えたりできるようになる、まさに夢のある時代です。
教育現場がAI活用を躊躇している間にも、テクノロジーは急速に発展して普及していきます。それならば、自分の能力を高めるための使い方を教師と生徒が一緒に考えたほうがAI時代を生き抜く人材を育てることにつながるのではないでしょうか。
(取材:IBS研究員 佐藤 有里)
【山中 司教授Profile】
立命館大学 生命科学部 生物工学科 山中 司 教授
専門は、言語コミュニケーション論、英語教育政策・教授法、言語哲学(プラグマティズム)。主に、プロジェクトの手法を用いた大学英語教育の有効性とその評価、機械翻訳や生成AIなどのテクノロジーを活用した授業について研究し、大学英語教育の改革に取り組む。慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 修士課程・博士課程修了。博士(政策・メディア)。立命館大学 生命科学部 生物工学科 准教授などを経て、2019年より現職。そのほか、立命館大学OIC総合研究機構 稲盛経営哲学研究センター研究員、「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」Research Group研究主幹なども務める。
※詳しい内容はIBS研究所で公開中の下記の記事をご覧ください。
前編: https://bilingualscience.com/english/2023092901/
中編: https://bilingualscience.com/english/2023100201/
後編: https://bilingualscience.com/english/2023100301/
【ワールド・ファミリー バイリンガル サイエンス研究所(IBS)について】
所長 : 大井 静雄
脳神経外科医・発達脳科学研究者ドイツ・ハノーバー
国際神経科学研究所(INI)小児脳神経外科名誉教授・医学博士
所在地 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド1階
設立 : 2016年10月
事業内容 : バイリンガリズムや英語教育に関する調査及び研究
ホームページ : https://bilingualscience.com/
公式X(Twitter): https://twitter.com/WF_IBS