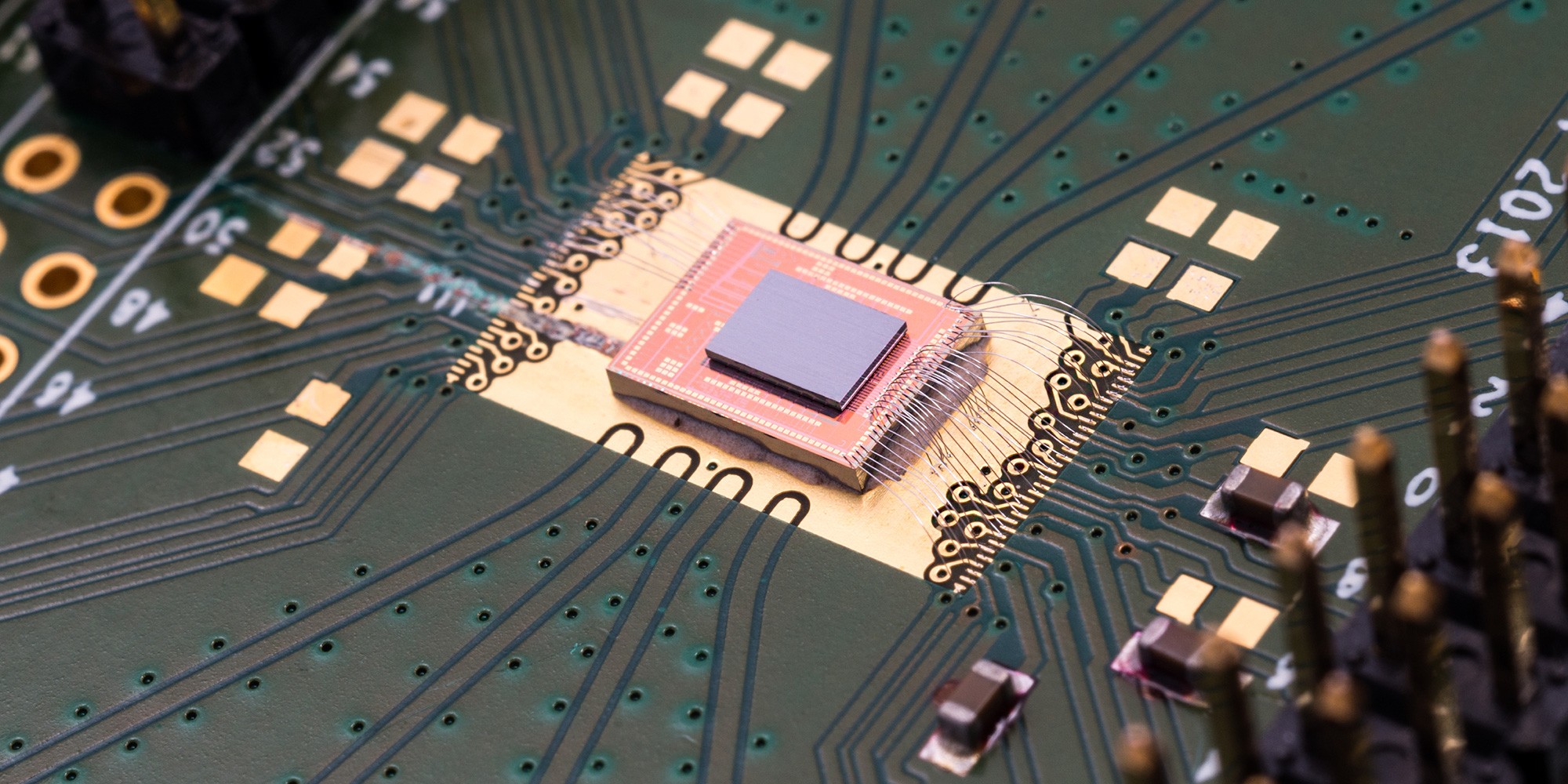原田PM採択プロジェクト最終成果発表会のお知らせ
企業動向
2005年8月22日 09:30報道関係者各位
2005年8月22日
IPA未踏ソフトウェア創造事業
原田康徳2004年度第2回目採択プロジェクト
独立行政法人情報処理推進機構2004年度第2回未踏ソフトウェア創造事業
原田PM採択プロジェクト最終成果発表会のお知らせ
◆概要
今回、行います最終成果発表会は、独立行政法人情報処理推進機構未踏ソフト
ウェア創造事業の原田プロジェクトマネージャー(NTTコミュニケーション科学
基礎研究所)が採択しました2004年度第2回開発者6名(グループ)の最終成果
発表会です。
独立行政法人情報処理推進機構(以下、IPA)は、日本のIT環境の推進を行って
おります。その中のひとつである「未踏ソフトウェア創造事業」は「IT人材の
育成」の一環として進められております。
IPAは、独創的なアイデアを持った個人の発掘を行うために、先進的な見地か
ら積極的に独創性を評価する、プロジェクトマネージャーを産学界から任用し
ています。当プロジェクトマネージャーは、自ら開発者募集要項を策定し開発
者を採択し、また開発期間中、指導・助言・評価などを通して開発者の人材育
成を行い、未踏ソフトウェア創設事業推進の一端を担っております。
IPAサイト: http://www.ipa.go.jp/jinzai/esp
今回の最終成果発表会では、原田康徳プロジェクトマネージャーが採択した6
名の開発者(グループ)の開発成果を発表いたします。開発者の開発成果の議論、
商談の時間をご用意しておりますので、是非、多くの方々にご覧いただき、今
後の開発の糧にさせていきたいと考えております。
記
◆日 時:8月30日(火) 午前10時30分開始(午前10時開場)
◆場 所:秋葉原クロスフィールドカンファレンスフロア5A会議室
http://www.akibahall.com/
◆参加費:無料
(メール・電話にて参加申込をお願い致します・定員50名先着順)
◆スケジュール・発表テーマ・発表者:
10:30-10:40 オープニング挨拶 原田PM
10:40-11:20 「源氏物語の鑑賞支援ツールの開発・整備」
宮脇文経 宮脇 清美 氏
11:20-12:00 「汎化冪空間類似度法による
データパーセプション技術の開発」
小林 卓夫 氏
13:00-13:40 「リアルタイム処理可能な汎用画像認識検出エンジン」
新妻 弘崇 氏
13:40-14:20 「物理法則を利用した動的形態の
プログラミング言語の開発」
古堅 真彦 氏
14:30-15:10 「かんたん映像編集ソフトをつかった
メディアリテラシー教材の開発」
杉本達應 宮原 美佳 氏
15:10-15:50 「キャラクターアニメーションに於ける
力感の自動補正ツール」
下平 和久 氏
16:00-16:30 総評・クロージング挨拶 原田PM
16:30-18:30 デモセッション
(デモを通じての発表者と参加者との間での質問やディスカッション)
◆成果報告会の問い合わせは下記までお願いします。(参加申込先)
IPA未踏ソフト創造事業原田プロジェクトマネージャーサポート組織
NTT出版株式会社情報デザイン企画室 黄金崎(こがねざき)
電話:03-5434-5513 FAX:03-5434-9101
e-mail: koganezaki@nttpub.co.jp
《ご参考資料》
最終成果発表会の開発概要
○「源氏物語の鑑賞支援ツールの開発・整備」 宮脇文経 宮脇 清美 氏
IT革命の進展に伴い、デジタル技術や情報技術、ネットワーク技術を活用して、
生活の質的向上を図ることが重要となっています。私は、最近、源氏物語に強
く関心を抱くようになりましたが、この分野では、まだ、IT革命の恩恵を十分
に活用しきれていないのが現状であると感じました。そこで、源氏物語の鑑賞
に役立つ各種の情報を、IT技術を駆使して使いやすい形に整理し、さらに源氏
物語に興味を持つ人たちの新たなコミュケーションツールにもなりうるソフト
ウェア「源氏物語の鑑賞支援ツール」を開発します。
現在、源氏物語の本文、注釈、現代語訳などを使いやすい形に整理して公開す
るWebサイトとして、「源氏物語の世界 再編集版」があります。そのサイト
では、高千穂大学の渋谷教授がWebサイト「源氏物語の世界」で公開している
源氏物語の本文、注釈、現代語訳などを読みやすい形式に再編集して公開して
います。
この再編集は、専用の再編集プログラムを作って行っていますが、現状では、
渋谷教授の本文、注釈、現代語訳に特化しているため、柔軟性に欠けています。
そこで、今回は、この再編集プログラムのデータ構造に着目し、それを整理・
改善して、新たなコミュケーションツールに必要な柔軟性を獲得することを主
目的とした開発を行います。
また、このプロジェクトの賛同者を募り、複数の人間が参画して源氏物語の鑑
賞に役立つ情報の整備を進めていくための環境も整備します。
○「汎化冪空間類似度法によるデータパーセプション技術の開発」
小林 卓夫 氏
本提案の主要なアイデアを一言で言うと、「時間計算量を空間計算量に転換す
る」ことにより大量のデータを高速に分析し、知的な処理を行うというもので
ある。
従来の代表的なデータ分析技術は、必ずしもデータ数に対して処理時間がスケ
ーラブルではないものが多い。それらの技術は理論的には確立されているが、
現実には限定した規模の範囲でのみしか適用することができない。大量の情報
を前にして、現在のITは時間計算量がネックとなってインテリジェンスの欠如
を起こしている。
そこで、本提案では、ムーアの法則等で予想された広大な記憶空間サイズを利
用して、空間計算量領域で解決することにより、データパーセプションと呼ぶ
べきITの知的処理のための技術レイヤ基盤を創出しようとするものである。
提案者が過去に発明した冪空間類似度法(特許取得済)を拡張した、「汎化冪
空間類似度法」(特許申請中)は、テラ規模のデータ数、メガからテラのカテ
ゴリー数の対象においてもリアルタイムに適用できる。この技術を用いて、本
提案の課題を解決する。
これにより、従来は扱うことの出来なかった領域で有効な作用が得られ、デー
タパーセプション・データインテリジェンスと言うべき、新しいフレームを創
出することができると期待する。
○「リアルタイム処理可能な汎用画像認識検出エンジン」 新妻 弘崇 氏
人間の脳の画像処理の仕組みは次の2つの処理で構成されている。1つは画像内
の目立つ部分のみを抽出するbottom-up処理、もう1つは意識して見つけたい
対象(特定の人の顔など)をみつけようとするTop-down処理である。
bottom-up処理は画像のsaliency-mapと呼ばれるものを計算することで実行さ
れる。
提案者は、Top-down処理を最尤推定として定式化する手法を過去に提案した。
このTop-down処理と bottom-up処理 の自然な融合を目指す。
この結果、画像データの目立つ領域のみの情報を利用することで検索する領域
を減らし、なおかつ、意識したい部分(認識したい対象)を高速に検出するこ
とが可能となる予定である。
本プロジェクトで作成するプログラムは、他の画像検出プログラムと比べて汎
用性と処理速度の速さに特徴のあるものとなる予定である。
○「物理法則を利用した動的形態のプログラミング言語の開発」古堅 真彦 氏
本提案は、コンピュータ画面上のオブジェクトの動きを制御するプログラミン
グ言語及びその実行環境を作ることを目的とし、その成果はウェブデザイナー
やコンピュータを駆使するアーティストなどいわゆるコンテンツクリエイター
と呼ばれる人たちによって活用されることを目的とする。
案者は、コンテンツクリエイターたちは、制作にコンピュータを駆使していな
がら、数学的知識が少なかったり、プログラミングスキルが少ない人が多いと
考えている。しかし、プログラミングや数学の知識を活用すればコンピュータ
は非常に強力なツールやメディアになり、彼らの中にもそこに魅力を感じてい
る人は多い。
また、コンピュータを取り巻く制作環境はその画面の表現手法に「動き」を多
用する場面が増えてきており、この「動き」を操る具体的な仕組みが重要にな
ってきている。現在のそれは複数の静止画を連続させる、いわゆるパラパラア
ニメーション方式が主流である。これは旧来の映画などの方式を拡張したもの
であり、コンピュータの特徴を十分に引き出しているとは言いがたい。また最
近ではウェブページやゲームなどに物理法則を利用した「自然な動き」が取り
入れられている。しかし上記のような理由から、その多くはパラパラアニメー
ション方式を使うか、数式やプログラミング部分をプログラマーに任せるいわ
ゆる「制作の壁」が生じている。
そこで本提案では、
・パラパラアニメーション方式等の従来の方式にしばられない
・物理法則を知らなくても物理的な動きを表現できる
コンピュータ画面上の動きを制御するプログラミング言語とその実行環境を開
発することを目的とする。
○「かんたん映像編集ソフトをつかったメディアリテラシー教材の開発」
杉本達應 宮原 美佳 氏
今日、人々がメディアを意識し、理解する「メディアリテラシー」の重要性が
議論されています。しかし、メディアリテラシー教育は始まったばかりで、十
分な教材がありません。
この状況を解決するために、映像の読み解きと活用・創造能力を習得できる、
あたらしいメディアリテラシーの教材を企画しました。
この教材で学ぶメディアは「映像」です。なぜなら、映像は、こどもたちが長
時間みてふれている、もっとも身近で大きな影響を受けているメディアのひと
つだからです。
教材では、こどもでも親しめる「カードゲーム」のスタイルで学習します。今
回の未踏ソフト応募では、この教材の核としてのカードインターフェイスによ
る映像編集ソフトウェアの開発および実践を提案します。
教材の概要
名称:「ムービーカード」
対象:小学生高学年から一般まで
「すべてのメディアは誰かによって編集されている」ことを、カードゲームで
遊びながら、学びます。
「ムービーカード」には、難しい知識や技術はまったく必要ありません。簡単
にメディアづくりを体験し、いろいろなゲームで遊びながら、映像メディアの
特性を理解したり、映像メディアを読み解く力を身につけます。
「ムービーカード」で遊ぶことによって、映像は同じ素材でも編集次第で全く
別の映像をつくりだせること、つまり、同じ出来事でも編集の仕方一つで全く
異なった印象のニュース映像ができあがることを学習できます。「ムービーカ
ード」を経験したユーザは、テレビ映像をただ漠然と見て受け入れるのではな
く、必ずそこには意図をもった編集者が存在していて、なんらかの偏向や加工
をなされている可能性があることを意識できるようになります。
○「キャラクターアニメーションに於ける力感の自動補正ツール」
下平 和久 氏
今日では3D-CG技術が発達し、大人も楽しめるCGアニメーション作品が多数製
作されている。こうした作品のアニメーションを支えているのは演技に関する
高度なノウハウを持ったプロのアニメーターやアクターである。このプロジェ
クトは彼等のノウハウをツール化し、手軽に利用できるようにすることを目標
とする。
今回採り上げるのは「パントマイム」のノウハウであり、これらのノウハウの
うち“クリック”と呼ばれる「力を入れる瞬間の小さな動き」と、キャラクタ
ーが「力を入れている動きと、力を受けている動きの表現分け」の2点をツー
ル化する。これら二つのノウハウは「アクションシーン」などで「力感」あふ
れるリアルなモーションを作るうえで重要である。しかも物理シミュレーショ
ンによる複雑な計算をかならずしも必要としないため、動作が軽いだけでなく、
使用者側の自由度が高いという特長を持つ。
本案件の範疇において、このツールは使用者が作成したモーションの任意の位
置に「力感」を「挿入」する機能を提供する。挿入対象となるモーションは事
前に作成する必要があるため、使いこなすためには「ポーズ取り」など絵画系
の技術が必要になるが、それでも多くのアニメーターたちが“よりリアルな”
表現を簡単に手にすることができるはずである。