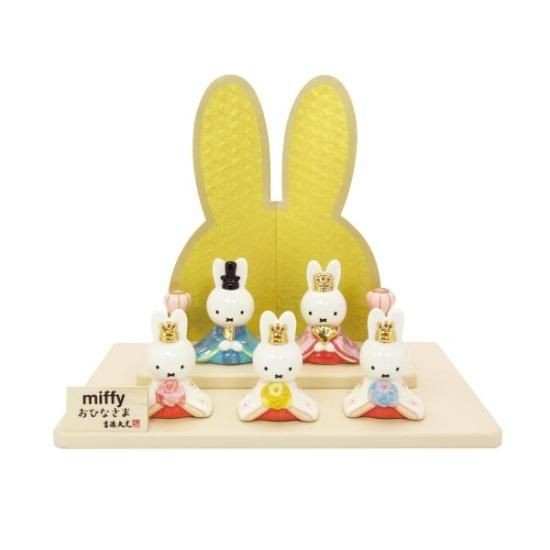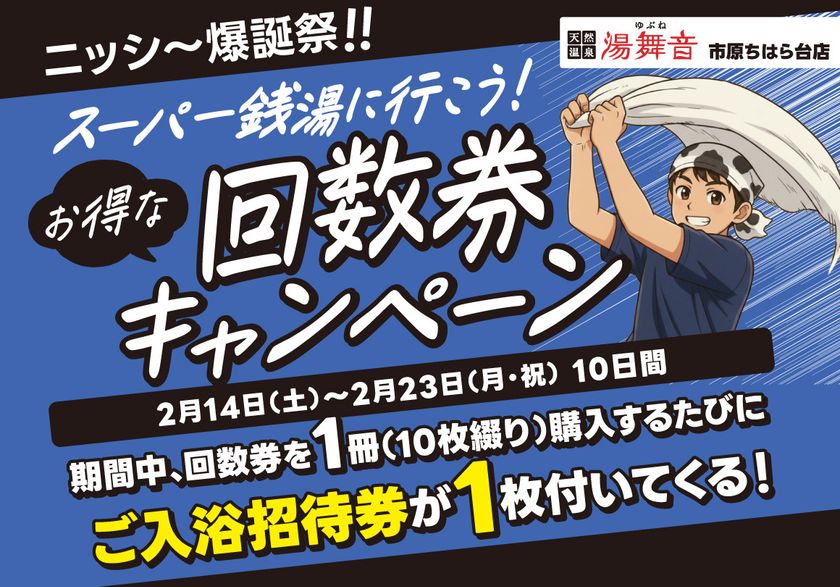お知らせしていました新橋花柳界が主催します 東をどり開幕がいよいよ明日24日(木)から27日(日)まで4日間開催いたします。本番の前日である本日23日、芸者衆は衣装に鬘を付け、白塗りに紅を引く芸者化粧で舞台ざらい(リハーサル)に臨みました。京都の舞妓・芸妓に比べてあまり知られる事の少ない東京の芸者衆ですが、実は匹敵する規模を持ちます。中でも新橋花柳界は東京六花街の筆頭、その東をどりは大正14年の初回から数えて今回で94回目の開催を迎えます。初日を前に本番さながらの舞台稽古を今回、初めて公開いたしました。新橋花柳界は銀座に架かっていた橋の名に由来する花街の名、実は新橋芸者とは銀座の芸者なのです。東京を代表する街、銀座にこんな日本があることは、あまり知られていないのではないでしょうか。観光客も多い国際都市、銀座の知られざる一面を御覧ください。




======================================
東をどりとは 歴史と背景
幕末に興った新橋花柳界。徳川贔屓の江戸の中、維新を前に薩長の志士を迎えました。明治になって彼らは政府の中枢、街は大きく発展します。芸の一流を街の目標に稽古を重ね芸処となります。京、大坂に在った芸者の歌舞練場に倣って、大正十四年に新橋演舞場を建設、東をどりが始まりました。戦火に焼けた演舞場、再建の復興、東をどりでは川端康成、吉川英治、谷崎潤一郎など文豪の脚本で舞踊劇に挑みました。踊りの名手、まり千代の美しい男姿が話題となり公演は大成功。楽屋口には出待ちの女学生の人垣が出来ました。芸の新橋は、一流の指導者と何より稽古に励む街の風が支えます。東をどりで街は一つになり、綺麗な芸と粋を散りばめて扉を開きます。
======================================
<第94回 東をどり 開催概要>
□日時:2018年5月24日(木)~5月27日(日)
24日・25日は二回公演
昼の席 開場12:30 開演13:00~終演14:30
夕の席 開場15:20 開演15:50~終演17:20
26日・27日は三回公演
壱の席 開場11:00 開演11:30~終演13:00
弐の席 開場13:10 開演13:40~終演15:10
参の席 開場15:20 開演15:50~終演17:20全10回公演
□会場:新橋演舞場 〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2
□前売り開始:4月7日(土)より
演舞場 切符売り場 他 松竹系プレイガイド
電話予約 チケットホン松竹:0570-000-489
インターネット予約:
Web松竹:PC http://www1.ticket-web-shochiku.com/pc/
携帯http://www.ticket-web-shochiku.com/
窓口販売・お引取り:新橋演舞場-切符売り場・歌舞伎座・大阪松竹座・
サンシャイン劇場
□チケット:桟敷席 9,000円/一階席 7,500円/二階正面席・二階右席 6,000円/ 二階左席・三階席 2,500円
※学生割引き:若い方に日本文化に親しんで頂くよう学生証をご提示頂くと当日券
は半額で販売します。
□公式:ホームページ:http://www.azuma-odori.net/



【演目紹介】
新橋は三流の家元にご指導を頂く土地柄、東をどりにも色を出せるよう総合演出を年ごとひとりの家元に委ねます。
今年は西川流の左近先生が、その役割を担います。構成は休憩を挟む二幕、今回は古典をテーマとした舞台です。
西川先生の談で古典は長くて退屈と思われがち、それを楽しんで頂くような工夫を凝らしたとの事です。古典とはど
こかで聞いたもの、すべては退屈するので良いところを繋げたと解釈しています。新橋芸者は古典をこなす実力が
あるからよ、と嬉しい言葉を貰いました。そして恒例のフィナーレ、これは左近先生のお父さんが作りました。芸者
衆は黒の引き着で舞台に並び、口上から観客を巻き込む手締めへ、踊りは俗曲「さわぎ」の節に乗せた東をどり
の名物です。芸者衆が客席へ手ぬぐいを撒いて演者と客席が一体となり、東をどりの幕を引きます。
「古典で見せる新橋の芸」 西川左近 総合構成・演出
□第一部 これが新橋長唄尽し
1,君が代松竹梅 (長唄) 尾上菊之丞 振付
若手10人による幕開きにふさわしい華やかさ、速いテンポに重厚さをのせる取り
合わせの妙を狙います。
2,雪月花 (長唄) 花柳壽應 構成振付/花柳壽輔 指導
昭和10年初演。しっとりした雪、粋な風情の月、派手に賑やかな花という変化に
富んだ舞台です。
□第二部 これぞ新橋清元尽し
1,吉田屋 (清元) 西川左近 振付
歌舞伎でお馴染みの夕霧伊左衛門の吉田屋座敷での恋のやりとり。炬燵くどきな
ど恋模様が見どころです。
2,女車引 (清元) 西川左近 振付
「菅原伝授」の車引の松王・梅王・桜丸を女房の千代・春・八重で見せる。駆け
出しから踊り地まで陽気で明るい舞台。
3,幻椀久 (清元) 西川左近 振付
大正14年の東をどりが初演。豪遊の果てに身を持ち崩した椀屋久兵衛が松山太夫
恋しさに物狂いを見せる踊り手の力量の要る演目です。
4,口上・フィナーレ 西川鯉三郎 構成・振付
昭和26年、西川鯉三郎が吉原に出向き「お宅の【さわぎ】を東をどりの舞台で踊
らせてほしい」と依頼。吉原組合の正式な許可を得て、歌詞を替えて作られた
東をどりの名物です。
◇本件に関する一般の方からのお問い合わせ先◇
東京新橋組合 TEL:03-3571-0012 (月~金 午前10時~午後5時)