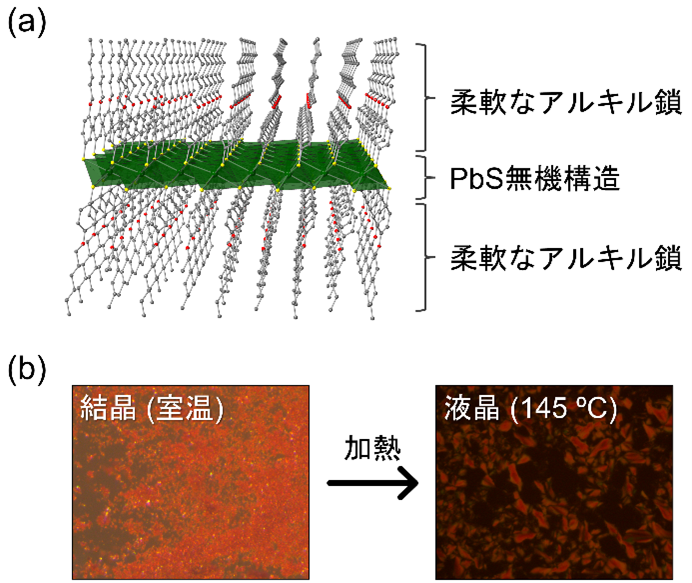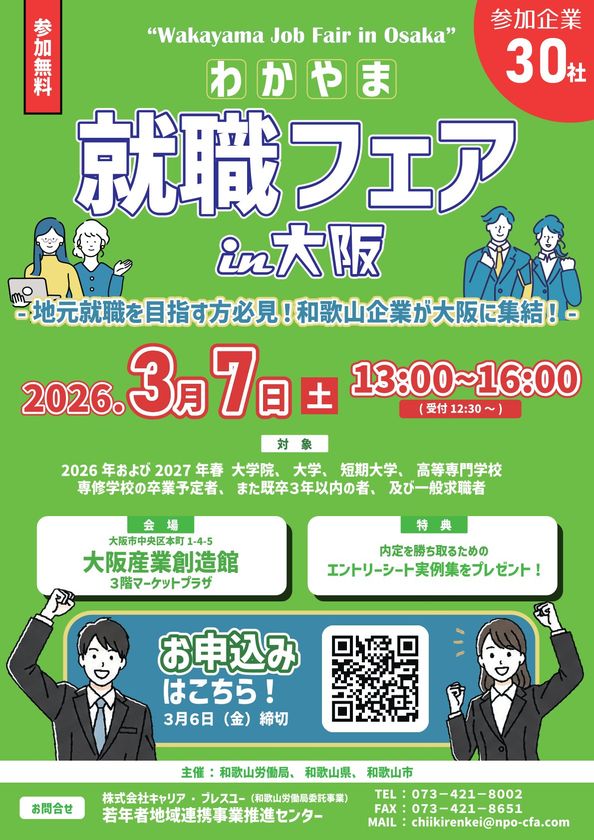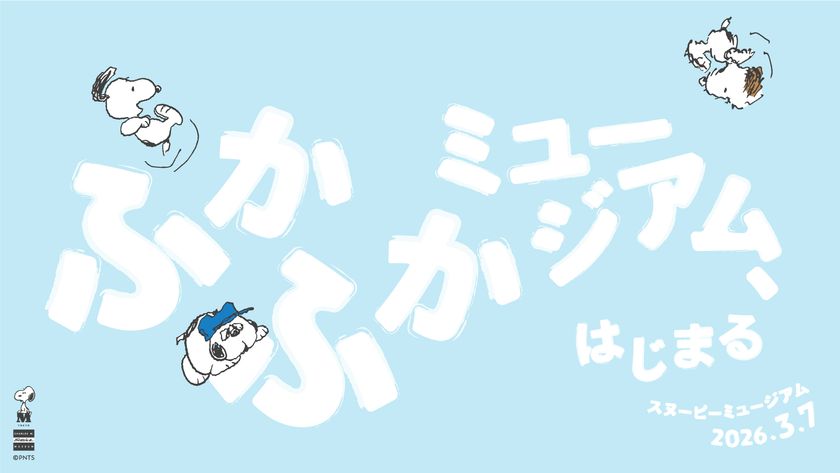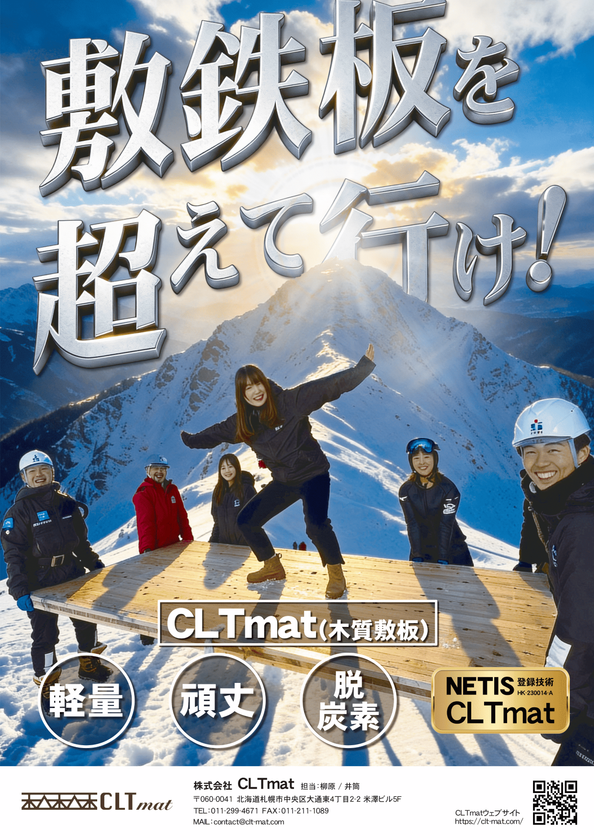ATMでの特殊詐欺被害防止策を近畿大学経済学部生が考案 行動経済学を活用した携帯電話使用抑止の検証結果を報告

近畿大学経済学部(大阪府東大阪市)経済学科教授 佐々木俊一郎ゼミ(行動経済学・実験経済学)は、一部改正された「大阪府安全なまちづくり条例」が令和7年(2025年)8月に施行されることに伴い、東大阪市役所危機管理室、大阪府布施警察署と協働で、ATMを用いた特殊詐欺被害の防止策について研究しています。
令和7年(2025年)6月20日(金)に開催される「第23回大阪府安全なまちづくり推進会議総会」において、学生が考案した防止策の検証結果を報告します。
【本件のポイント】
●「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正に伴い、官学協働でATMでの特殊詐欺被害防止策を検討
●経済学部生が行動経済学の知見を活用して考案した、ATM操作中の携帯電話使用抑止策の効果を検証
●今後、制作物を改良し設置範囲を拡大することで、特殊詐欺被害防止への貢献を目指す
【本件の内容】
大阪府では一部改正された「大阪府安全なまちづくり条例」が令和7年(2025年)8月に施行され、高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することが禁止となり、また、ATM設置者にもその対策措置が義務化されます。
近畿大学経済学部の佐々木ゼミ(行動経済学・実験経済学)、東大阪市役所危機管理室、大阪府布施警察署は、ATM操作中での携帯電話使用を抑止するため、行動経済学で注目されている「ナッジ」に着目しました。ナッジとは、行動科学の知見から、人々により良い行動を選択してもらうように誘導する仕組みであり、その提唱者であるシカゴ大学のリチャード・セイラー教授が平成29年(2017年)にノーベル経済学賞を受賞したことで注目を集めています。
佐々木ゼミの学生は、ナッジを活用して、ATMにおいて利用者が自然に携帯電話を使用しなくなるよう、携帯電話を使用している自分の姿を見て、その使用を抑制するためのミラーカード、目の写真を印刷したシート、ATMの前で携帯電話を使用しないための誘導看板を制作しました。その制作物を、令和7年(2025年)5月20日(火)、27日(火)の2日間、銀行のATMに設置し、効果を検証しました。その結果、1時間あたりの携帯電話使用平均人数が減少し、ATM利用者へのアンケート調査の結果から、携帯電話使用の抑制に一定の効果があったことが確認されました。この結果を、「第23回大阪府安全なまちづくり推進会議総会」にて、大阪府知事や大阪府警察本部長らに報告します。
今後、検証結果を踏まえて制作物を改良し、設置範囲を拡大することで特殊詐欺防止への貢献を目指します。
【実施概要】
日時 :令和7年(2025年)6月20日(金)10:30~12:00
場所 :ホテルプリムローズ大阪 2階「鳳凰の間」
(大阪府大阪市中央区大手前3-1-43 Osaka Metro谷町線・中央線
「谷町四丁目駅」から徒歩約1分)
報告者 :近畿大学経済学部経済学科教授 佐々木俊一郎
近畿大学経済学部佐々木ゼミ学生 21人(報告者は2人)
参加予定:大阪府副知事
大阪府警察本部長
ほか構成団体代表者多数
主催 :大阪府、大阪府警察
【「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正】
近年、大阪府内では特殊詐欺被害が急増しており、被害者の大半を高齢者が占めています。令和6年(2024年)の大阪府における特殊詐欺の認知件数は2,658件であり、その被害総額は約64億円にのぼります。特殊詐欺の犯行は、携帯電話による指示でATMを操作させて金銭を振り込ませる手口や、コンビニ等でプリペイド型電子マネーを購入させて騙し取る手口が多く発生しています。こうした状況を踏まえ、大阪府では「大阪府安全なまちづくり条例」を一部改正し、金融機関や事業者、府民等に特殊詐欺被害等の防止対策が義務付けられました。条例改正によって特殊詐欺の被害防止への対策が強化されたのは、以下の4点です。
①高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することを禁止:ATM設置者は禁止のための措置を講じる義務があります。
②金融機関による通報等:金融機関は特殊詐欺などの被害のおそれを認めた場合、警察に通報する義務があります。
③ATMでの振込上限額の設定:ATMでのキャッシュカードによる振込が1日あたり10万円以下に制限されます(70歳以上、3年間ATMでの振込なし等の条件あり)。
④プリペイド型電子マネー販売時の確認:5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。
【関連リンク】
経済学部 経済学科 教授 佐々木俊一郎(ササキシュンイチロウ)
https://www.kindai.ac.jp/meikan/203-sasaki-shunichirou.html