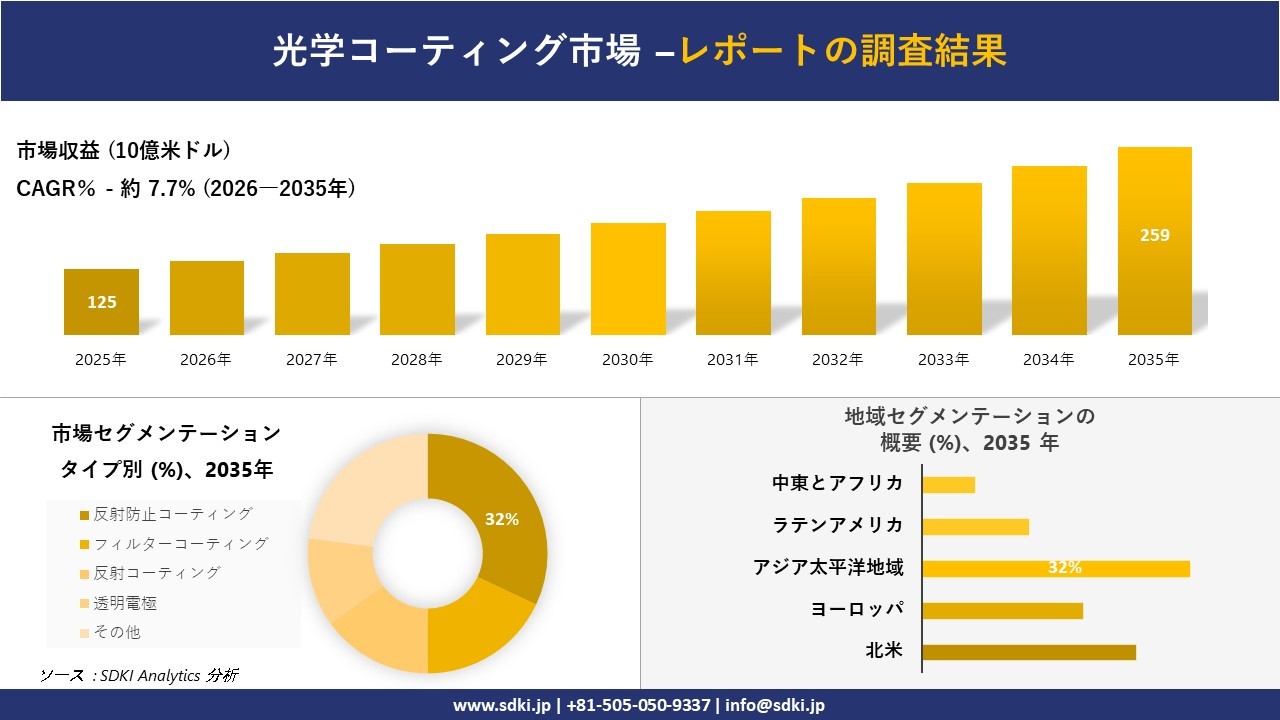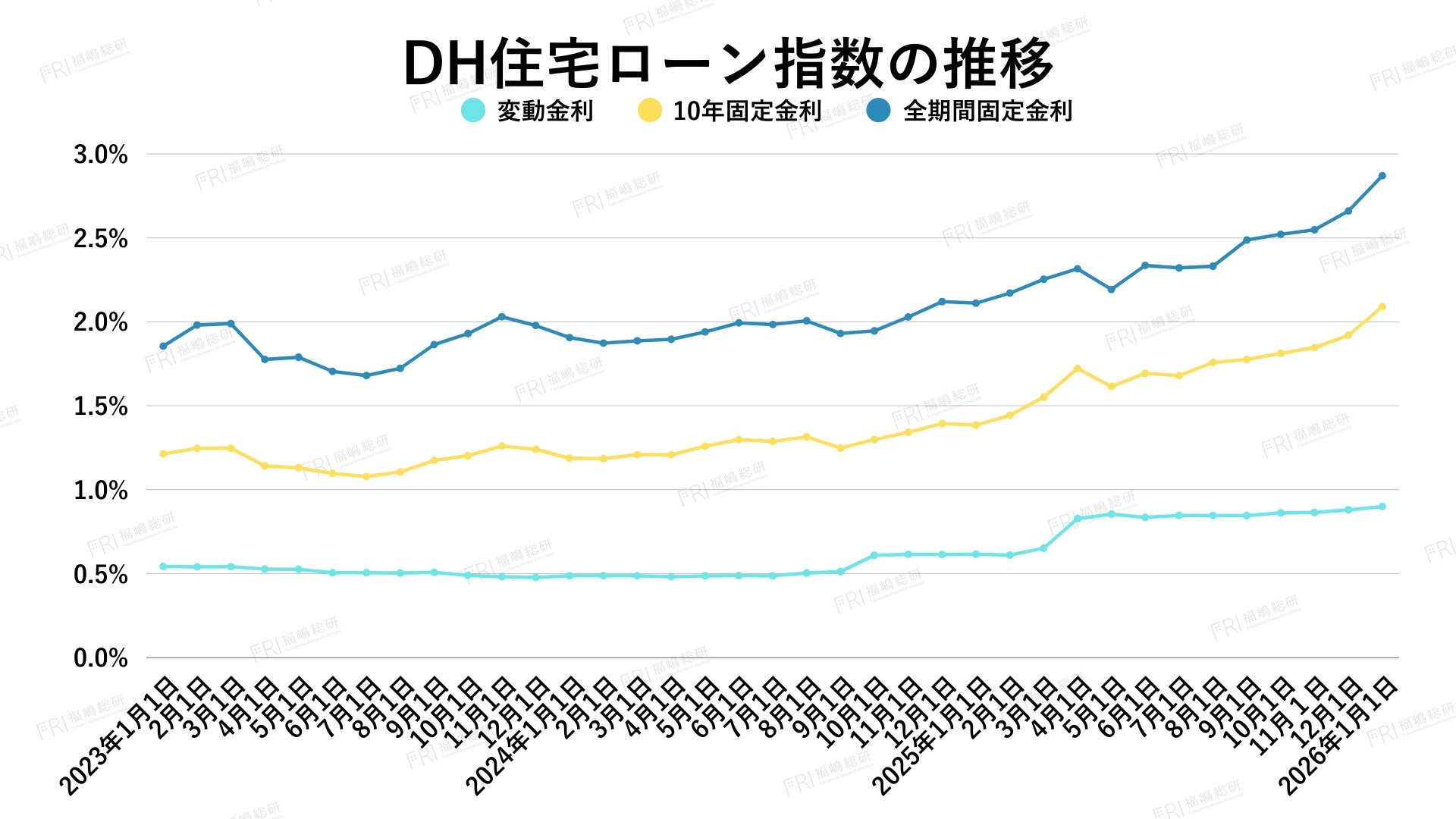【名城大学】災害食をお土産に! アイデアピッチコンテスト受賞までの葛藤と実現化を見据えて
「災害時でも食べたいものを食べられる環境に!」をコンセプトに、防災食の開発を目指すPolaris。“いかにも非常食”というものとは一線を画し、お土産として贈りたくなる、デザイン性を兼ね備えた「お土産×災害食」の商品開発にチャレンジし、「Tongaliアイデアピッチコンテスト2025」で「名鉄賞」を受賞しました。
4人のメンバーが、立ち上げからコンテスト参加までの長い道のりと、受賞の先に見据えているものについて語り合いました。

Polarisメンバー
篠田裕太さん/理工学部 社会基盤デザイン工学科3年生
高 麻由さん/理工学部建築学科2年生
山住望恵さん/農学部生物資源学科2年生
野崎友莉子さん/経営学部経営学科2年生
声を掛けたのは同じ価値観を持つメンバー
「そもそも最初はまったく違うプロジェクトでスタートしたのです」とPolarisの立ち上げを先導した篠田さん。1年生から上級生のOur Project(注1)にも参加していた篠田さんは、当初Our Projectで取り組んだ奈良県山添村の“村おこし”をテーマにするつもりでした。
1年間かけて進めていくプロジェクトなので、同じ熱量で同じ価値観を持っている人でなければ続かない。経験から篠田さんは、“この人”と思う人に積極的に声をかけていきました。

野崎:一緒にやりたいと言われ話を聞くと、山添村の村おこしプロジェクトでした。もともと地域づくりに興味があったので参加を決めました。
高:私は建築で村おこしに関われるかと思って加わりました。
山住:食の分野で村おこしに関わってほしいと、声をかけられました。いろいろな学部の仲間と一緒にできるのも面白そうだなと思って。
4人は2度ほど山添村に足を運びみんなでアイデアを出し合う中、やがて壁にぶつかります。
中間発表で他のチームが「これがやりたい!」とかなりの熱量で語っている姿を見て自問したそう。「山添村のプロジェクトは面白そうだけど、自分ごととして考えられているだろうか?」
みんなの興味のあることをやろう!
話し合いを重ねる中で、メンバーそれぞれが描く方向性や熱量に違いがあることが見えてきました。
「これは本当に自分がやりたかったことなのか?」
「拠点が遠いと頻繁に活動できず、結局は誰かに任せっぱなしになってしまうのでは…?」
篠田さんは葛藤しながらも、思い切って「みんなが本当に興味を持てることをやろう!」と方向転換を決断します。
4人があらためて想いを率直に語り合った結果、ついに全員がワクワクできる共通テーマ『食』にたどり着きました。
野崎:メンバーに偏食が多かったため、偏食で本当に困る時はいつか?と考えた結果、「災害時」というキーワードが浮かびました。
高:災害時でも自分が好きなものが食べられたら元気になれるよね、というところから「お土産」という次のキーワードが出てきました。
そこで旅先のお土産コーナーで災害食になりそうなものを集めると、その多くは缶詰でした。ただ缶詰ってあらためてパッケージを見ると「買いたい」と思えないのです。まして、お土産として渡すにはちょっと気が引ける。特に女性は買いたいと思わないよね、という話になりました。お土産として渡せる災害食があればいいのに、と考えたのです。
「Tongaliアイデアピッチコンテスト2025」で「名鉄賞」を受賞
篠田さんは課題解決に取り組むならボランティアではなくビジネスとして成り立つ形にしたい、という思いを持っていました。そこであえて「Tongaliアイデアピッチコンテスト2025」への参加を決心しチームメンバーに打診。全員賛成でプロジェクトが一気に進み始めます。

篠田:書類審査の段階では「お土産×災害食」というコンセプトと、缶詰製造の委託先の確認のみで、具体的に商品化までは進めていませんでした。ただ、準決勝まで進むとビジネスとして市場規模やマネタイズの手法なども求められます。顧客は誰なのか?その人たちは本当に災害時に困っているのか、といった根拠となるデータを提示しなければならず、時間がかかりました。
メンバーは講師や防災士からのアドバイスを受けてブラッシュアップを重ねた結果、高倍率の準決勝を見事突破。決勝へと駒を進めます。決勝での最終結果は「名鉄賞」を受賞。しかし素直に喜べるメンバーはいませんでした。

質疑応答の場で、審査員の一人から鋭い問いが投げかけられます。
「君たちは賞を取りたいだけなのですか? それとも、形にして顧客に届けたいのですか?」
篠田さんは迷わず「形にして届けたいです」と答えました。
すると審査員は続けます、「それなら、ユーザーエクスペリエンスをもっと考えてみては?災害食は“保存するもの”だから、お土産として渡しても、すぐには食べてもらえない。お土産を受け取った側は、普通はすぐにお礼を伝えたいもの。そこに生じる“ズレ”をどう解消しますか?」
その指摘は、これまでの自分たちにはなかった視点だったそう。4人は今後形にしていくためには避けて通れない課題だと強く感じたそうです。
決勝のハイレベルな他のチームのプレゼンを聞く中で、それぞれ感じるところもあったようです。
篠田:学内の発表では自分たちがやりたいことをプレゼンすればいいのですが、アイデアピッチでは「届けたい」「買ってほしい」と、外に向けた話になります。お客さんや投資家の時間を奪ってまで、自分たちは何を提供できるのかということを明確に伝えるという意識が必要だと気づかされました。
山住:私たちよりも短いスパンで商品化しているチームもあり、他のチームのプレゼンからは絶対に実現してやる!という思いの強さを感じました。私たちはアイデア頼りで奥行きや説得力がなく、まだまだ本気でやりたいんだ!という強さが足りていない気がしました。
高:他のチームは巻き込み力が違う、私たちには巻き込む力が全然足りていないと感じました。
外部からのアドバイスを推進力に
コンテストの参加で火がついた4人。講師に相談したところ「いきなり缶詰を作るのはハードルが高いので、お土産用のパッケージラベルを作って貼ってはどうか?」というアドバイスをもらい、まずはラベルシールを作ることから始めました。
どこまで災害感を出すか?と災害感とデザイン性のバランスに悩みます。地産地消の災害食は存在しますが、「名物」に寄せていきたいです。あとは差別化をどうするか、まだまだ考えるべきことはたくさんあります。と篠田さんは語ります。

今後については、他のビジネスコンテストにも挑戦したいと4人は前向きです。
最終目的の「アイデアを形にする」に向かって、ブラッシュアップを重ね、商品化まで持っていきたいと意気込みました。
名城大学だったからできたこと、出会えた仲間
高:実は名城大学は第一志望の大学ではなかったのですが、名城大学という総合大学に来て、いろいろな学部の人と話し、交わり、多くの知識を得られました。中でもいろいろな学部の子が集まる、今回のようなプロジェクトに参加できるのは、とても貴重だと思っています。
野崎:頑張ろうと思ったら、頑張れる場を大学が提供してくれるのがありがたい。チャレンジプログラムで全学部の人と繋がりができて、構内を歩けば必ず知り合いに会うなんて、想像もしていませんでしたから。
山住:私もいろいろな人と関われるのが嬉しい。このプログラムに参加していなかったら、もっとゆる〜く生きていたと思います。私より頑張っている人がいるから「頑張らなくては!」と思えます。自分を追い込むことも、ある程度は必要なことだと学びました。
篠田:総合大学で人数も多いから、尖った人もいます。それがおもしろい。やりたいことは何でもできるし、社会連携センターに行けば外部との繋がりも作れます。職員も学生をいつも応援してくれる。この環境があるから、こういうプロジェクトもできるんだと思います。
今回、コンテストに参加したことで、頭の中のモヤモヤが整理されたと、全員の意見が一致。審査員に「形にして届けたい!」と決意を述べたからには、やるしかない!熱量も考えもバラバラだった4人が一枚岩となって次のステージに向かって動き出しました。
(注1)リーダーとしての素養を身に着ける少人数制の『名城大学チャレンジ支援プログラム』2年目に実施される学生による自主的な企画・取組