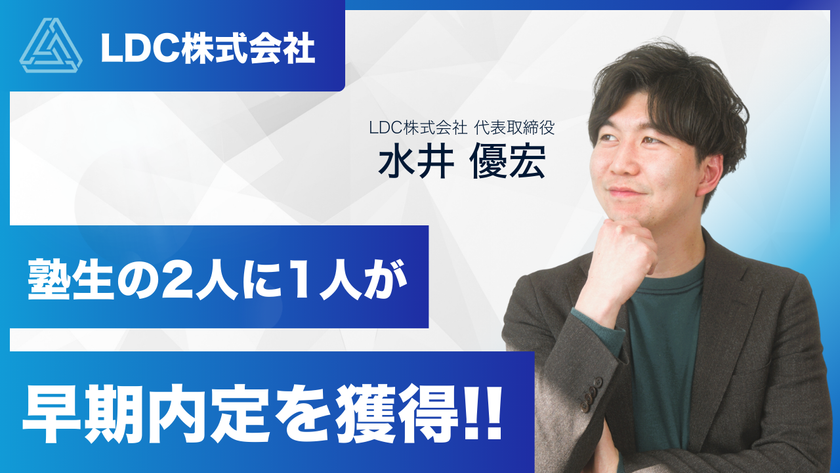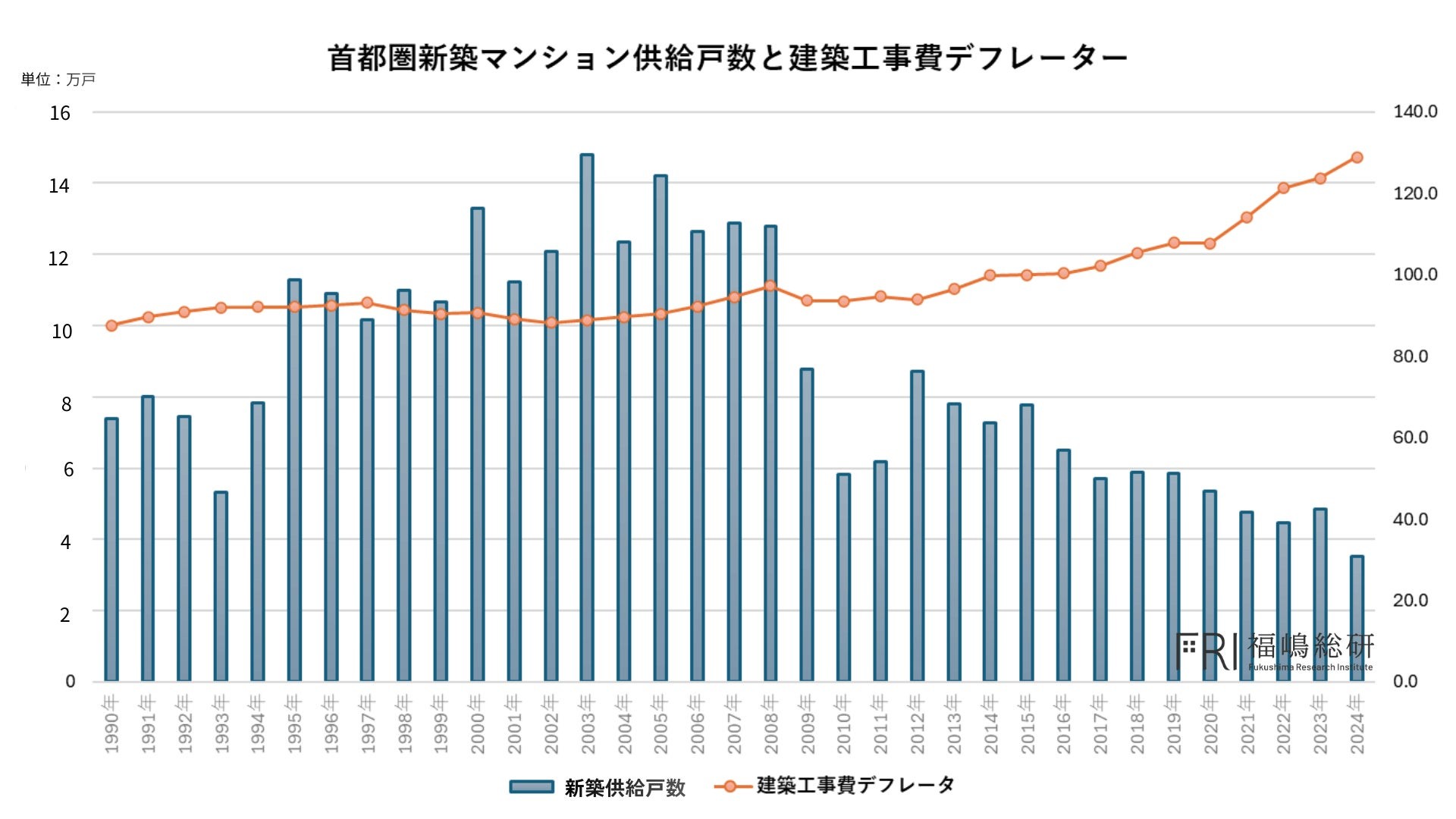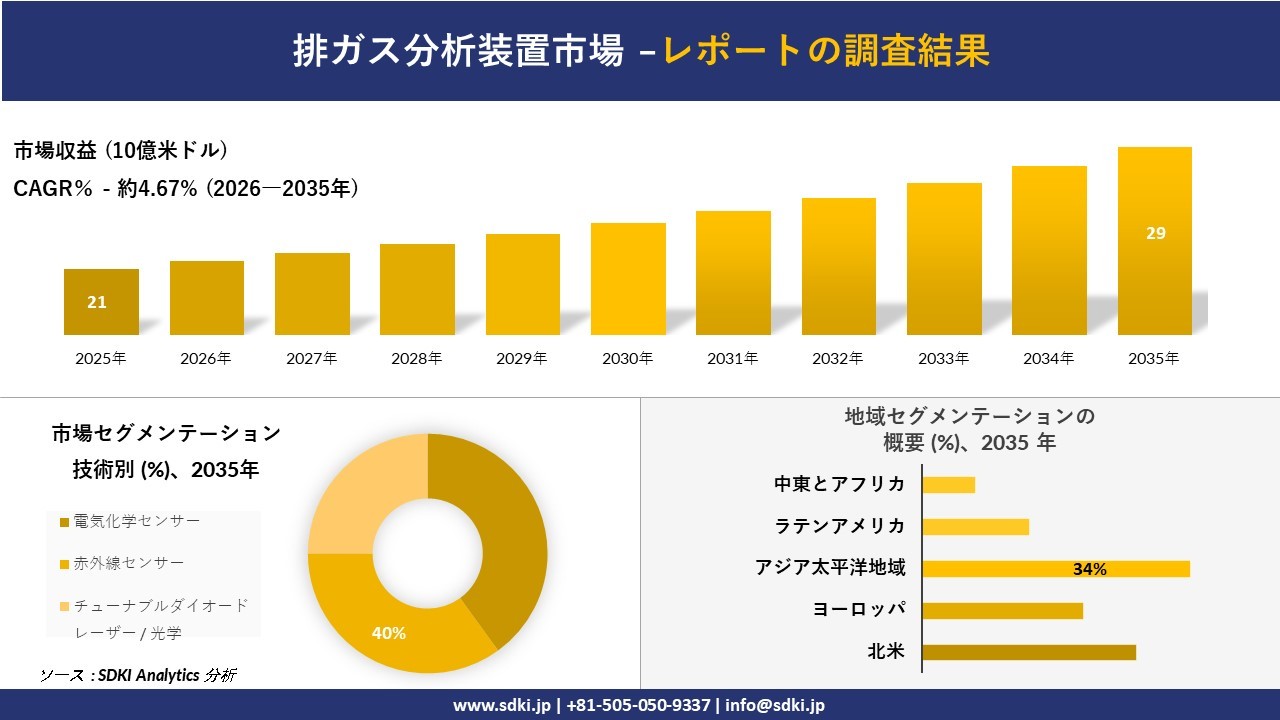<繊維to繊維>次世代の反毛技術で、いらなくなった 繊維製品から作った災害用備蓄毛布が、ふるさと納税に初登場
リサイクル繊維毛布「真空パック包装ひざ掛け」が 泉南市のふるさと納税返礼品に選定
丸竹コーポレーション株式会社(代表取締役社長:立花 克彦、本社:大阪府泉南市樽井7丁目21番13号)は、これまで難しかった反毛綿(はんもうわた)から生地へのリサイクルの実用化を可能にいたしました。
反毛綿から毛布への再生など、起毛が必要な製品への再生も可能になりました。
いらなくなった毛布・制服・繊維製品を、紡績にかけられるレベルの高品質な反毛綿(繊維原料)に加工することにより、毛布の原料として使用することができます。
【次世代の反毛技術で作った災害用備蓄毛布が泉南市のふるさと納税返礼品に選定】
リサイクル繊維で製造された毛布、商品名サスティブブランケット(ひざ掛けサイズタイプ)が泉南市のふるさと納税返礼品に選定されました。
真空パック包装で圧縮することにより、備蓄しやすいコンパクトサイズになりました。また清潔に長期保存が可能です。

サスティブブランケット
【サスティブブランケット(難燃)】
原材料 :【緯糸】モダクリル70% 再生反毛30%
【経糸】ポリエステル100%
サイズ :90cm(横)×70cm(縦)
重量 :400g
寄附価格:15,000円
【丸竹の新技術なら、あらゆる繊維で“反毛ワタから生地”が可能に!】
いらなくなった繊維を無数の針で引っ掻いてバラして綿(わた)にすることを反毛(はんもう)、出来た綿を反毛綿(はんもうわた)と言います。
従来の反毛綿は、反毛することで繊維の長さが短くなり、元の状態よりも品質が下がってしまうため、糸に加工することが難しく、用途が限られていました(フェルト・芯地・太糸の軍手など)。
丸竹の最新設備では、化学繊維や天然繊維、混紡繊維など、どんな繊維でも細かく分解されて、リサイクルされた反毛原綿として生まれ変わります。
反毛綿から糸へ、糸から生地へ、そしてリサイクル繊維毛布へと生まれ変わります。

繊維製品を繊維原料へ

いらなくなった毛布が生まれ変わるまで
【次世代の反毛技術で品質、風合い、耐久性、バージン繊維毛布とほぼ同等】
従来の反毛の技術は、針で引っ掻く前に、縦にも横にも繊維を細かく裁断します。そして、いくつもの工程を経るため、そのたびに繊維が損傷します。また工程ごとに繊維くずが大量に発生します。繊維長も元より短くなります。
丸竹の次世代の反毛では、工程数を減らしたことにより、繊維の損傷を抑えました。
繊維の開繊度が高いため、繊維の細かさは従来の倍以上でバージン原料と見間違うほどの高品質な反毛綿が出来上がります。
裁断するのではなく、引き裂くことにより、繊維長を従来品より長く残すことができ、強度も風合いもアップしました。
これまで反毛には5台の機械が必要でしたが、連結した1台で可能になったため、繊維くずが激減し、原料を無駄なく使用できます。
反毛綿とバージン原料とを相応しい割合でブレンドして紡績し、糸の番手を変えることで、バージン繊維毛布とほぼ同等のクオリティが可能です。

最新設備によるリサイクル工程
【従来の反毛綿は、細い糸にすることが出来なかった】
従来の反毛綿は細い糸にすることが出来ませんでした。
細い糸を作るには「空気精紡」という高速回転する機械が必要なのですが、従来の反毛綿は繊維長が短く、繊維自体の波型波形(クリンプ)も伸びきってしまっているため、空気精紡にかけることが出来ません。
しかし丸竹の反毛技術で製造した反毛綿は空気精紡にかけることが可能なため、糸にすることができ、これまで不可能だったリサイクルも可能になりました。

繊維の細かさは従来の倍以上
【日本防炎協会認定の難燃性を備えています】
反毛綿とバージン原料とを相応しい割合でブレンドして紡績し、日本防炎協会認定の難燃性を備えさせました。期限切れや廃棄予定の毛布からの再生の場合、ラベルやヘムごと100%再利用可能となりました。

バージン繊維毛布とほぼ同等の品質
【リサイクル前に洗浄&除菌W効果のクリーニングを自社工場で行います】
気持ち良く使っていただきたいから、丸竹ではリサイクル前にクリーニングを自社工場で行います。
地球環境に優しい電解水衛生環境システムのクリーニングを採用しています。
洗浄力&除菌力、W効果の「電解水」を使用。まず「アルカリ性電解水」で、細菌の温床や臭いの元となるたんぱく質・油脂汚れを分離分解、そして「酸性電解水」で菌を除去します。

クリーニング風景
【丸竹の反毛技術なら、企業や自治体から出る不要になった繊維製品を繊維原料に戻せます】
現在多くの企業や自治体が環境問題に真剣に取り組み、ゴミの削減、CO2削減、資源循環を目標に掲げています。捨てずに再生させることで、産廃費用を削減しながら、自社のSDGsやESGの環境問題へのアプローチに「繊維の再生」を活用することができます。
反毛綿への再生過程では、化学薬品をほとんど使いません。また最新設備により従来に比べ工程数が減るため、エネルギー消費が抑えられます。
丸竹では再生可能エネルギー(CO2排出ゼロ)を100%使用しているため、地球環境に優しいリサイクルが可能です。

SDGsやESGの環境問題へのアプローチに1
【繊維製品の資源循環の手段として、再び注目される反毛技術】
欧州委員会は2020年3月、「持続可能な循環型繊維戦略(EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles)」を策定。
2030年までにEU域内で販売される繊維製品を、耐久性があり、リサイクル可能で、リサイクル済み繊維を大幅に使用し、危険な物質を含まず、労働者の権利などの社会権や環境に配慮したものにするという目標を掲げています。
経済産業省も令和5年11月のレポートで、「我が国の繊維産業が、引き続き、国際競争力を維持し続けるためには、欧州等における環境配慮や繊維リサイクルに適合した取組を支援しつつ、我が国が世界に先駆け繊維リサイクルシステムを構築し、欧州等のルール形成にも貢献していくことが重要」と述べています。
このように日本でもサステナビリティ推進の動きが高まっています。
そのようななか、繊維製品の資源循環の手段として、再び反毛技術が注目されています。

SDGsやESGの環境問題へのアプローチに2
【市民投票により泉南市の「ええもん せんなんもんプレミアム」にも認定】
災害用備蓄毛布、商品名サスティブブランケットは、泉南市観光協会が主催する「ええもん せんなんもん2023」の認証を2023年3月に取得しています。
「ええもん せんなんもん」とは、地域の経済活性化や観光振興を目的として、地域で生産された優れた商品やサービスを「ええもん せんなんもん」と認証し、全国の消費者や事業者にアピールする制度です。
イベント会場(イオンモールりんくう泉南店)とネットで行われた市民投票での結果、サスティブブランケットが全得票数の過半数を超えた票数を獲得。
その後、2023年11月には、まちのブランドとしてシティプロモーションを促進しうる魅力を有するものに与えられる「ええもん せんなんもんプレミアム」にも認定されました。

左:立花社長/右:市長
【社会課題である繊維製品の資源循環に貢献】
「本来BtoB向けの商品である当社のサスティブブランケットが、ふるさと納税や、ええもん せんなんもんプレミアムの認定を頂くことができたのは、当社の繊維再生技術が、社会課題である繊維製品の資源循環に貢献できると評価していただけたのだと思います。
今後も重ねて、地域の経済活性化に貢献するため、より良い商品やサービスを開発してまいります」と丸竹コーポレーションの立花 克彦社長はコメントしました。
【受付サイト】
■楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/f272281-sennan/10001335/
■その他掲載サイト
ふるさとチョイス・ふるなび・ANA・セゾン・まいふる
【詳細情報】
丸竹コーポレーション株式会社
■ホームページ
https://www.marutake-corp.co.jp/
■リサイクル繊維毛布WEBページ
https://www.marutake-corp.co.jp/service/ecoproject/project01.php
■繊維再生WEBページ
https://www.marutake-corp.co.jp/service/ecoproject/project03.php